縁友往来Message from Soulmates
- 縁友往来
- エコノミカル・コレクトネス
エコノミカル・コレクトネス

この1月にトランプ氏が第二期目のアメリカ大統領に就任して以降、世界は大きく動き始めている。ガザ地区では停戦合意が成立し、ウクライナ戦争も休戦の可能性が見えてきた。カナダとメキシコには早速関税が課せられ、日本に対しても関税が課せられる見通しである。
もしハリス女史が大統領になっていたなら、この様な世界の急速でダイナミックな変化は起こらなかったであろう。
トランプ大統領はアメリカの伝統であったポリティカル・コレクトネス(政治的正義)に捉われない政治運営を初めて行った大統領だと言われている。ポリティカル・コレクトナスとされた多様性に配慮した教育や社会制度にも躊躇せずに政治的介入を行っている。
この政治姿勢はエコノミカル・コレクトネス(経済的正義)に対してもとられていると思われる。
戦後世界のエコノミカル・コレクトネスは「自由競争・自由貿易」であった。そしてこのエコノミカル・コレクトネスが最も大きな影響力を持ったのが1980年代、1990年代だったと思う。そのピークはウルグアイラウンドの時期だったであろう。
ウルグアイラウンドは1986年に始まり1994年に終結した多国間貿易交渉である。この合意を受けて1995年にはWTO(世界貿易機関)が設立された。
ウルグアイラウンドの時期は「自由競争・自由貿易」が世界の潮流となり、それを疑問視する者はほとんどいなかった。
経済学ではリカードの「比較生産費説」以来、自由貿易は貿易国双方に経済的便益の増加をもたらすことが常識とされてきた。第二次世界大戦勃発の背景には、世界恐慌時に先進各国がブロック経済化したことがあることを指摘されると、誰もが自由貿易をエコノミカル・コレクトネスとして認めざるを得ない雰囲気が醸成されていた。
私はウルグアイラウンドの時期にOECDの農業委員会作業部会に出席していたが、当時の作業部会で進められていたことはAGLINKと呼ばれる世界農業モデルを構築し、これを使って貿易自由化の影響を計量的に推計しようという試みであった。
国際会議の前には、必ず我が国の対処方針を決めて会議に臨むのだが、私が命じられた対処方針はAGLINKモデルに絶対にコメを組み込ませないということだった。
コメが組み込まれると我が国のコメ産業保護によって、コメ輸出国が被っている経済的損失が具体的な数字として明らかになり、これは我が国のコメ市場開放への圧力となることが懸念されていたからである。
日本はまずオレンジの自由化を受入れ、次に牛肉の自由化を受け入れていた。ウルグアイラウンドではこれまで日本農業の聖域とされてきたコメの自由化が議題に挙がっていた。
この時期の農林水産省の最大の課題は、この貿易自由化の世界的潮流をどう乗り切り、国内農業を守るかであった。
ウルグアイラウンドでは最終的に日本のコメのミニマムアクセス(最低輸入制)が合意された。
1999年にはこのミニマムアクセスは関税制に移行されて現在に至っている。高い関税率が設定されたこと、最初輸入されたタイ米やベトナム米は食味の問題で日本の消費者に不人気であったこと、国内米価が低く据え置かれたこと、円安が進んだこと、食味の良いカリフォルニア米や黒竜江省米は本国で需要が急増し、輸出余力が低下したことなどにより、日本のコメ産業が壊滅的な打撃を受けることはなかった。
ウルグアイラウンド当時のことを振り返ってみると、現トランプ政権の貿易政策は大きな転換である。トランプ政権の政策運営は複雑でその方向性がなかなか見えないのだが、最終目標は「アメリカ・ファースト」による自国の繁栄であろう。
このスローガンには、他の国も自立国家としてまずは自国の繁栄を追求しなさいというメッセージが含まれているように思われる。エコノミカル・コレクトネスの呪縛が緩んだこの時期を好機と捉え、自立国家として重要な産業や自然を場合によっては相互関税も援用して保護し、それを育生していく経済政策を整えるべきである。
2025/3/24

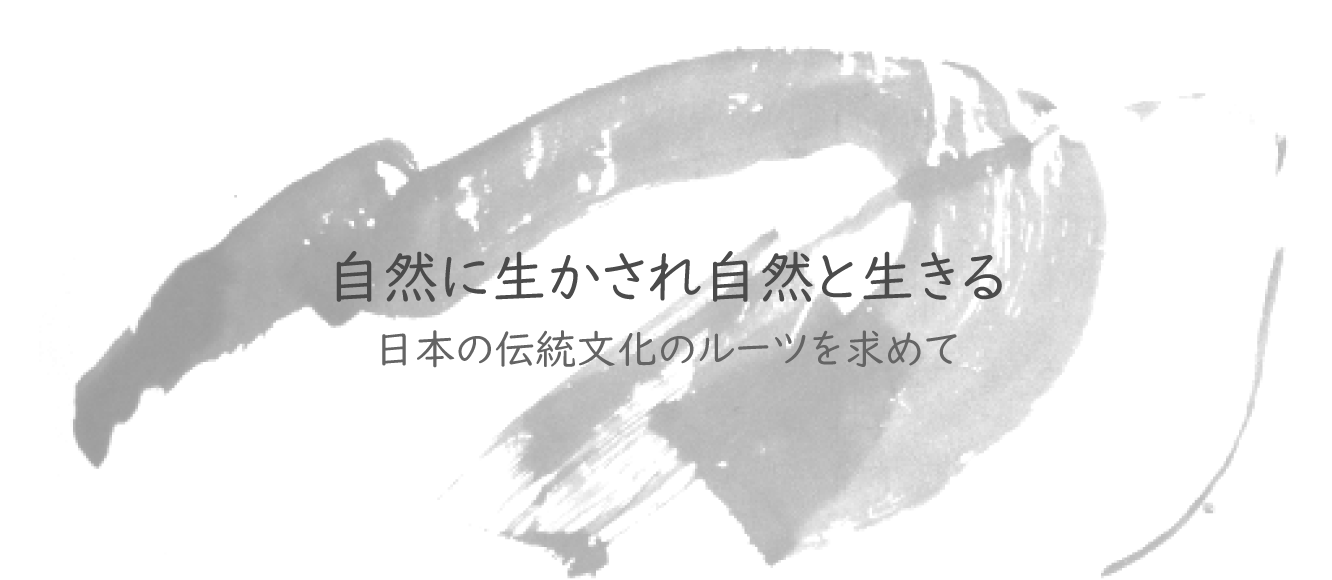
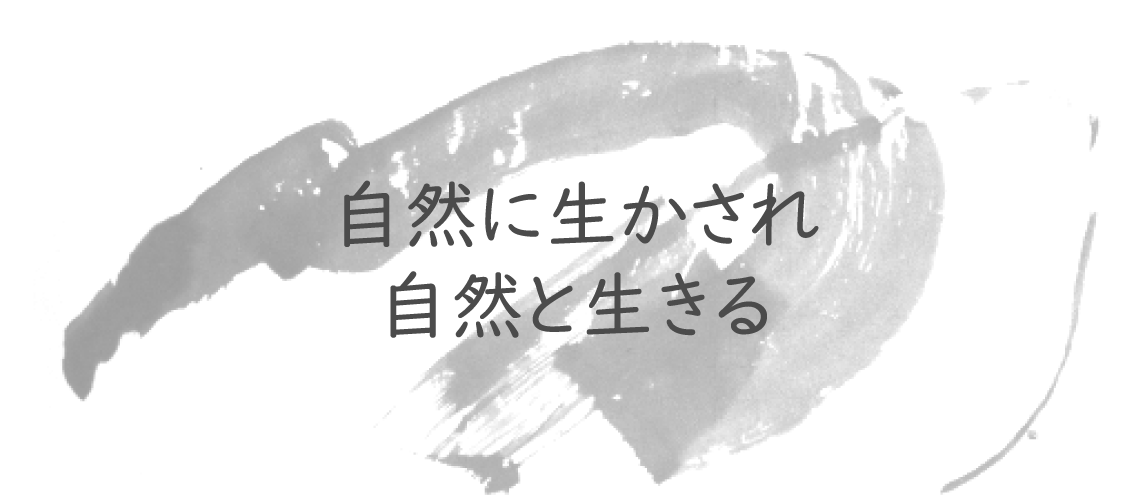
Comment
1980年代から1990年代、私が生きていた場所とは全く違うところで、当たり前のように毎日食べていたお米をめぐる駆け引き行われていたことは全く知りませんでした。
私たちが見ている「この世」の姿は、それをどこから見ているのかによって、大きく変わります。
同じ時代を違うステージ生きてきた縁友たちが、それぞれが体験した「人生」を持ち寄れば、私たちがどんな時代を生きてきたのか、その全体像がより明らかになってゆくのではないでしょうか。
縁友のネットワークによって描き出される全体像が、「劣化した日本」のピンチをチャンスに変えてくれることを祈っています。
コメント投稿には会員登録が必要です。