縁友往来Message from Soulmates
- 縁友往来
- 令和の米騒動
令和の米騒動

今回の「令和の米騒動」は、昨年の8月から始まった。
それまでの数年間、うるち米の小売価格は、5kg2500円前後で安定的に推移していた。しかし8月に入って、台風予測と南海トラフ地震警報情報が出されてたのを契機に、消費者は例年の4割増の米購入を行った。民間流通在庫は、2022年の218万トンから2024年は153万トンに低下していたので、米の品薄感が広がって小売価格が上昇を始めた。
8月には2900円に上昇し、9月には3300円、10月には3700円、11月には3900円と上昇を続け、12月には4000円を上回って、その後高止まりしたのである。
この価格高騰に対処するために、江藤農林水産大臣は今年の2月から政府備蓄米の放出を始めた。31万トンの政府備蓄米を公開入札制で売却したのだが、米の小売価格は上昇をつづけた。
4月に入って江藤大臣の「私は米を買ったことがない」発言が問題視され、江藤大臣は事実上更迭され、小泉氏が新農林水産大臣に就任した。
小泉大臣は、政府米備蓄の公開入札制をやめて随意契約制に切り替えて、30万トンの放出を行った。この変更により、店頭には5kg2000円の備蓄米が出るようになり、銘柄米の小売価格もようやく下落を始め、4000円を下回るようになってきた。
以上が、今回の「令和の米騒動」の経緯である。我々はこの「令和の米騒動」から何を学ぶべきなのか、少し考えてみたい。
この30年間ぐらいで米価格高騰が起こった事例が3回あった。
1993年の「平成の米騒動」と2003年の冷夏による米価高騰、今回の「令和の米騒動」である。1993年の米価高騰は冷害による米生産量の30%の減産により起こった。2003年の米価格高騰も冷夏による15%の減産により起こった。しかし今回の「令和の米騒動」は2024年の作柄指数101もとで起こっている。作柄指数は100が平年作を示すので、作柄は平年並みだったのである。
ではどうして米価格高騰が起こったのか、その主な理由は民間流通在庫量が少ない中で8月に台風予測と南海トラフ地震警報情報が発動され、消費者が米買付に走ったことによる。2024年に民間流通在庫が減少していた背景には、2023年が夏の高温と渇水のため減産と品質低下が起こったことがある。特に銘柄米での品質低下が著しく、品薄感が広がっていた。政府は民間流通在庫の低下にもっと注視し、2024年の米作付けをもっと増やすよう奨励すべきであった。
江藤農林水産大臣のもとで今年の2月から政府備蓄米31万トンの放出が行われたが、米価下落は起こらなかった。これは、31万トンの95%を公開入札でJAが買い取ったが、JAは小泉新大臣の就任時点までに買い取った政府備蓄米の5%しか卸売市場に流通させなかったためである。
JAが政府備蓄米を流通させなかった背景には、年間約700万トンと見込まれている米需要市場に政府備蓄米31万トンが追加流入されることによる米価格の下落を恐れたためであろう。米市場は、需要の価格弾力性が極めて小さい市場である。わずかな供給量の増減でも大きな価格変動が起こる市場である。
米の需要価格弾力性は-0.1よりも小さいと推察されるが、例え-0.1と仮定しても、10%の供給量の減少によって、100%の価格上昇が起こることを示している。実際に昨年8月から1月までに米価格は1.6倍上昇したが、同期間に米需要量は前年よりも逆に若干増加している。米の需要価格弾力性が極めて小さいことには、留意すべきである。
現在でも米流通の4割を占めているJAが備蓄米を抱え込んで米価下落を避けようとしたことには倫理的な問題が残るが、米生産者の立場からすると、これまで生産者米価が低く抑えられてきたという重大な問題もある。ウルグアイラウンドが始まる前年の1985年の生産者米価は5kg当たりで1530円であった。それが40年たった現在の生産者米価が1280円で、16%下落している。この40年間に多くの物材費は上昇したにもかかわらず、生産者米価だけは下落している。
この小稿を書くために米関連の資料を調べてみたが、どういうわけか生産者米価の長期的推移を示す図表を見つけることができなかった。農林水産省も何かを忖度しているかのように、このように大切な生産者米価の長期的推移を示す図表を公表していない。まるで生産者米価が40年間にわたって低く抑えられ続けた事実を隠ぺいしたいかのようである。
日本農業を本当に守りたいのなら、まずは米価の適正水準についての議論を本格化させるべきである。
2025/6/25

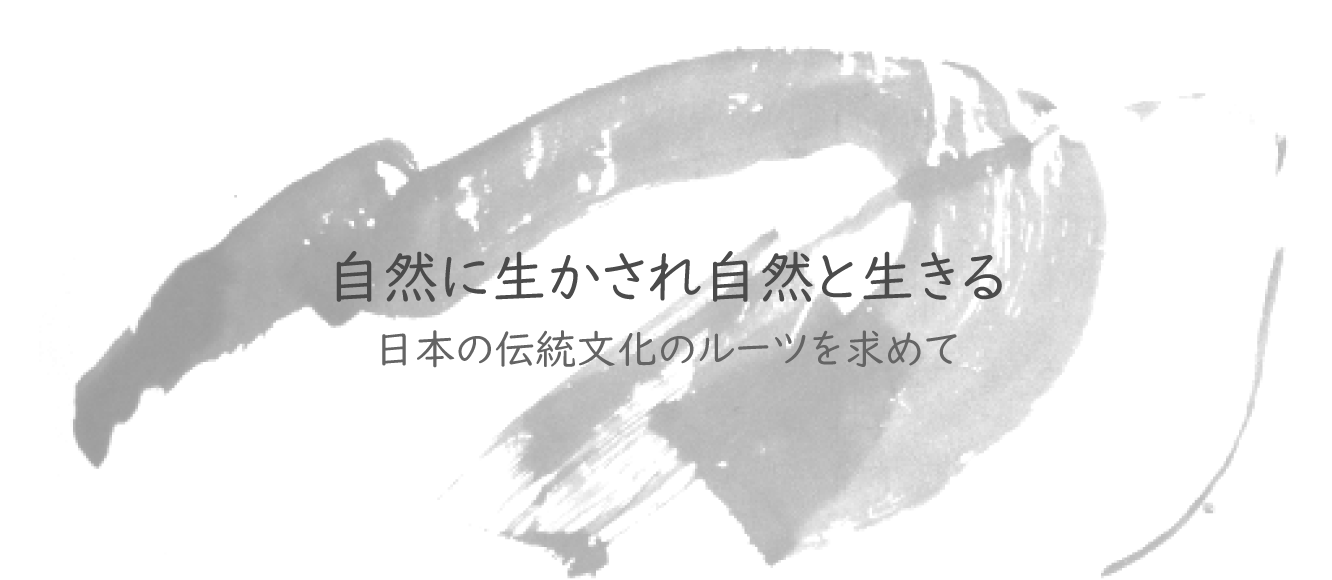
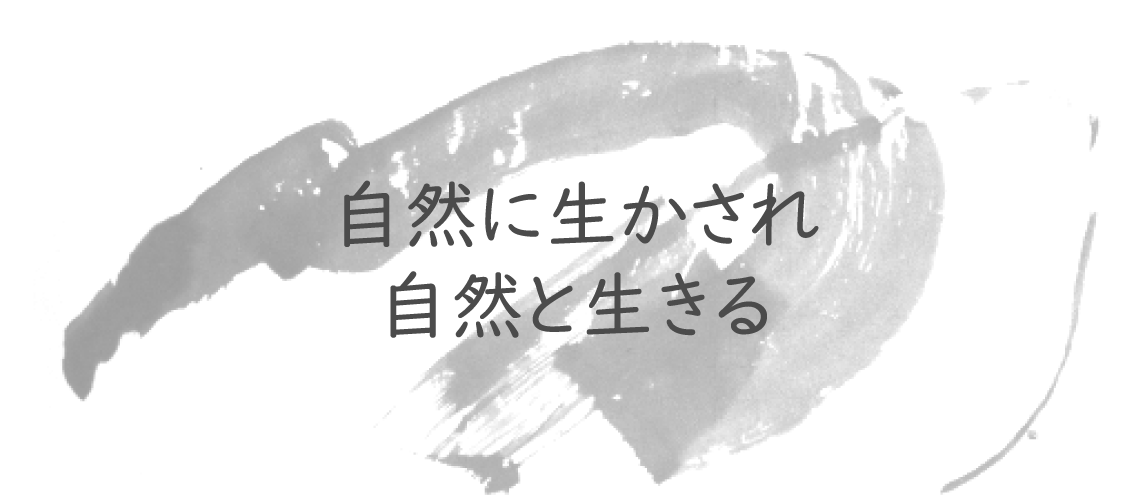
Comment
とにかく、日本のお米は、美味い。農家の皆
さんに、この場を借りて、まず感謝します笑。
日本人にとって、お米は生命の糧である。
元気の「気」の字は、もとは「氣」であった。
戦後、日本人の氣(精神力)をそぐために、
米が、〆(しめる)へ━、氣が、気に変えら
れたという話がある。そのほか、神にまつ
わる幾つかの漢字も、禁止になっている。
命を養う米を、締め切る意味の〆に変え
た意図は、米は、命の中心から、生命の
エネルギーが四方に発揮される様を現す。
逆に、〆は、エネルギーを締めて、閉じ込
める意である。確かに、昔の日本人に比し
現代人の元気、気概、気力は衰えている。
日本人の命の根源的エネルギーを養い
発揮させる大もとになる米が、満足に食
べられない状況が起きている。異常だ。
危機的な状況である。日本で4、5000円
する日本の上級米が、アメリカで2500円。
古古古米を、カビ検査も省いて流通させ、
ある量販店が独自に検査したところ問題
があり販売をとりやめたという情報もある。
が、オールドメディアは、一切報道しない。
皆さんも、何が真実なのか、自分で情報
を集め、考え、行動されるように、切にお
願いする次第である。お気をつけていた
だきたいと思う。
また、流水氏には、日本人と米、日本文化
と米との切っても切れない深いつながりに
ついて、今後も教えていただければと願う。
中川さん
NATURE JAPAN ゆっくりと観ました。普段、せかせかと時間が過ぎていくような生活をしているので心が洗われるようでした。
ありがとうございます。
流水さんの寄稿を拝読しました。
3回ほど繰り返し読んだのですが、まだ理解できない箇所があります。
農家さんが長きにわたり苦しめられ続けてきたことはわかるのですが、農水も含めて「統計を開示してない」というのはどういうことなのでしょうかねぇ。
今回のJAの買い占めと出し惜しみは、相変わらずの体質なのですか?
素人には分からないことが多すぎです。
小山拝
小山賢二さま
石川先生の奥日光の動画や拙稿を見て頂き、有難うございます。皆さんに勝手に紹介して、恥ずかしい限りなのですが、一人でも見てもらえる方がいて、大変励みになります。
「令和の米騒動」ですが、伝えたかったことは三つあります。一つは、昨年8月からの米高騰と高止まりの原因は、昨年の民間在庫水準が低かった中で8月に台風予測と南海トラフ地震警報情報が発動され、8月の消費者の米購買量が4割増加したことが契機となったこと。また2023年が猛暑で特に銘柄米の品質が低下して、銘柄米の品薄感が広がっていたことです。
二つ目は、江藤農林水産大臣の下で政府備蓄米が31万トン放出されたにもかかわらず、米価が上がり続けた原因には、31万トンの95%を落札したJAが5%しか市場に放出しなかったこと。この背景には、米市場の需要価格弾力性は極めて小さく、供給量の僅かな変化でも大きな価格変化が起こる市場であることです。
三つ目は、今回の令和の米騒動で気づいたこととして、この40年間生産者米価が低く据え置かれてきたことです。
私はこれまで農水省やJA関係者にずいぶんお世話になってきた者なので、JAの批判はしたくないのですが、米価高騰を抑えるために放出した備蓄米31万トンのほとんどを抱え込んだままにしたJAの今回の行動は記憶されるべきだと思いました。
それから今回気が付いたのですが、農家は5kg1500円で売っている米が、小売価格では4500円になっている不思議です。いくら流通経費がかかるといっても3000円の格差は異常だと思います。
ウルグアイラウンドが始まる前年の1985年までは、生産者米価と消費者米価はほぼ同じでした。これがこの40年間にこんなに大きな生産者米価と消費者米価の格差が生れたことに改めて気づきました。既得権益集団による国家的な中抜き構造の典型と言われてもしょうがないと思います。これまで自民党の農林族議員は何をしていたのでしょうか。
農水省は米に関しては、ありとあらゆる種類の統計を公表しています。しかし、この生産者米価と消費者米価の長期的推移の図表については、いくら探して見つけられませんでした。このような大切な統計を公表させない、既得権益集団からの圧力を感じました。
この30年間にアメリカのGDPは3倍に、中国は20倍に増加したのに、先進国の中で日本だけがほとんど伸びていません。新生児出生数も70万人を切りました。皆な一生懸命働いてきたのに、また日本人は優秀で勤勉な民族なのに、どうしてこんな凋落が起こっているのかを考えたとき、日本経済の中抜き構造の蔓延化が一つの原因に思えてなりません。我々年寄りは、これまで生きてきた経験から、次の世代に大切なことはきちんと伝えていくべきだと考えています。
(中川)
中川さん
ご丁寧な説明ありがとうございます。
かなり分かりました。
それにしてもJAなどという巨大な存在は組み換えした方が良さそうですね。
JAや卸、小売りといった複雑な流通構造がコメの値段を高くしているのでしょうね。ドンキの社長が政府に提言書を提出したようですが、そろそろ既得権をはく奪した方がいい時代になってきているのでしょうね。生産現場も大きく変わろうとしているのですから。
小山拝
小山賢二さん
貴重なコメント有難うございます。小山さんのような海外でのビジネスに精通された方から見ると、日本経済の歪みがよく見えるのでしょう。東大教授の鈴木宣弘さんは、今の日本経済は「今だけ、金だけ、自分だけ」の考えが支配していると指摘しています。
今回の備蓄米放出をめぐってはJAの行動は批判されるべきで、また農林水産大臣にJA解体論者の小泉氏が就任したことから、JAの株式会社化がにわかに現実味をおびてきました。しかし私は改革は必要ですがJAは協同組合の形で存続してもらいたいと願っております。
日本のJAは生産・共同購入販売・銀行・共済の機能を担う総合農協なのですが、世界で総合農協が残っているのは日本だけです。これは日本の地域共同体の紐帯力が他の国に比べて非常に強いからと言われており、地域共同体の紐帯化にJAは貢献しています。
私は30年以上JAの準会員として、自動車保険や健康保険、住宅保険に入っていますが、料金は安いと思います。JAが解体ではなく改革されることを願っています。今回の令和の米騒動は農業食料分野の歪みを浮彫にする契機となったと思います。
(中川)
中川さん
10年後に農業従事者の年齢構成はどのように変化するか見通しはあるのですか?また従事者総数や作付面積についても同様に明るい見通しはあるのですかねぇ。
心配です。
ウチは30年以上前から秋田県大潟村の農家から直接コメを買っています。
とても美味しいお米です。
でも先月注文したら今は在庫が無いという話でした。新米は8月以降の注文受付となるようです。
昨日、スーパーマーケットでコメを買いましたが、あきたこまちは無く、山形の銘柄米を4320円で買いました。やっぱり高いのですね。
とりとめもない話でした。
小山拝
小山賢二さん
我々が学生の頃は、日本の農家数500万戸、農地面積500万haと記憶していました。現在の農家数は175万戸、農地面積は427万haです。農家数が大きく減りました。ただ農家一戸当たりの経営規模は拡大しています。農業就業者の平均年齢は69歳で、65歳以上が7割を占めています。10年後にはこの7割がリタイアするので、農家数はさらに減るでしょう。
茨城大で務めていた時、国際農業開発研究室を経営していました。近くの農家さんから10アールの農地を借りて10年間米の栽培を行いました。30種類以上の品種を栽培していました。その時は農地を貸してくれた農家さんからお米を買っていました。今回、生産者米価と消費者米価がこんなに開いていることを知って、私も今年の新米は農家さんから直接買おうと思います。直接買うことが農家さんにとっても消費者にとってもウィンウィンですね。
(中川)
コメント投稿には会員登録が必要です。