縁友往来Message from Soulmates
- 縁友往来
- ネパールとのご縁
ネパールとのご縁

私のネパールとのご縁は、大学最後の年に仏跡巡礼でルンビニを訪れた時に始まる。
農林水産省への入省が内定していた2月に、インド哲学研究者の藤井教公(現在北大名誉教授)さんと3週間かけてインドの仏跡を巡礼した。お釈迦さんが悟りを開いたブッダガヤや初転法輪の地のサルナート、涅槃の地のクシナガラなどの仏跡を巡礼して廻ったが、その際に誕生地のルンビニも訪問した。
お釈迦さんはインド人として知られているが、誕生地のルンビニはネパールにある。インドからネパールに入国したが、当時は国境といっても長い竹竿を上げ下げするゲートがあるだけだった。入国事務所でビザの印を押してもらいネパールに入った。
お釈迦さんはヒマラヤ山脈の麓に居住していた釈迦族の第一王子として誕生した。その後王位を継がずに出家し、修行の末に悟りを開いて仏陀となった。
米を常食とする釈迦族は、純粋なアーリヤ系というよりもモンゴル系の血も混ざった部族なのではないかと推測する。ルンビニには現在も釈迦族が住んでおり、大学も創って仏教の伝統を守っている。深い朝霧の中の蓮花が神秘的で美しかったことを憶えている。
ネパールとの二度目のご縁は、パンディ(Pradyumna Pandey)君との出会いに始まった。当時私は茨城大学農学部に勤務していたが、ある日一人の留学生が私の研究室前の廊下をまるで禅僧が経行しているかのように静かに歩いている姿を見かけた。少し冷やかしてやろうと声をかけたのだが、その学生がパンディ君だった。
廊下での立ち話で、彼はJICAの奨学生として茨大に来たこと、修士論文は既に完成し、あと2か月で帰国することを知った。彼はヨーガを実践していることも知った私は、彼に尋ねた。
「ヨーガを実践しているのなら、パタンジャリーの『ヨーガ・スートラ』を知っていますか」と。彼は答えた、「我々ブラーミンは、小さい頃からサンスクリット語を学び、『ヨーガ・スートラ』はサンスクリット語で暗記しています」と。「それでは、『ヨーガ・スートラ』の内容は分かりますか」と尋ねてみた。
彼は正直に「難しくてよく分かりません」と答えた。「私は『ヨーガ・スートラ』の良い解説書を持っているので、貴方にそれを紹介しましょう」と言って、彼を私の研究室に案内した。
研究室に入ってきた彼に、私は本棚から和尚(Osho)の『ヨーガ:アルファ―からオメガまで』を取って渡した。それを受け取ったパンディ君は、しばらくすると手が震えだし、「私は実はこの和尚の弟子です」と語った。
『ヨーガ:アルファからオメガまで』は10冊本で、私はすべての原書を持っていた。学生のころアルバイトでお金が入ったら、すぐに西荻窪のプラサード書店に行ってこの原書を買っていた。この本がとりなす彼との不思議なご縁を感じた。
それからパンディ君は、夕方になると私の研究室を訪ねてくるようになり、色々な話をした。
JICAの研修期間が終わり、いよいよ帰国する前に彼は私に言った。
「私はネパールでは農業開発省の次官補をしており、本来の私の専門は農業経済学です。私は再び来日して、先生の下で博士号を取得したい」と。私はJICA奨学生とは異なり、私費留学生は経済的に大変であることを説明したが、私費留学でもいいから博士課程に入学したいとのことだった。
結局パンディ君は、約束通りに再び来日し、その年の10月から東京農工大学大学院連合農学研究科の博士課程に進学した。彼はほとんど手のかからない模範的な学生で、自主的に研究をどんどん進め、『ネパールの米産業の展開と課題』で博士号を取得した。
彼が私の研究室に馴染んできたころ、彼は何度も家での夕食に誘うようになった。初めは断っていたのだが、何度も誘われるので一度よばれることにした。彼が住んでいた県営アパートを訪ねると、奥さんのナム(Namrata Pandey)さんがありとあらゆるベジタリアン料理を用意して待っていた。
楽しく歓談して帰ろうとしたら、ナムさんが言った、「先生、私も博士課程に入学したい」と。
私はパンディ君一人の私費留学だけでも大変なのだから、ナムさんの進学はしばらくたってからにした方がいいと説得した。しかしナムさんの決意は固く、最後には私が根負けして、ナムさんも次の年に博士課程に入学することになった。ナムさんもまったく手のかからない模範学生で、『ネパールの観光業による地域開発の課題』で東京農工大学から博士号を取得した。
その後、パンディ夫妻の紹介で私の研究室には3人のネパール人学生が入ってきた。ラム(Ram Ghimire)君は、やはり農業開発省の次官補で、『ネパールの農産物輸出の課題』で博士号を取得した。ドール(Dor Rayamajhi)君も次官補で、『オレンジ産地形成による地域開発の課題』で博士号を取得した。
シュレスタ(Balaram Shrestha)君は、日本在住の国際弁護士で、『ネパールの女性小規模金融の効果と課題』で博士号を取得した。現在日本在留のネパール人は18万人いるが、シュレスタ君はこのネパール人コミュニティのリーダーである。シュレスタ君との関係で、私も時々ネパール人コミュニティの活動に参加している。AGRIの本部は、シュレスタ君の両国のオフィスに置かせてもらっている。
ヨギ―でもあるパンディ君とナムさんは、ネパールに帰国後アッチャラヤ(阿闍梨)の資格を取り、現在隔週毎にZOOMで「日本瞑想セッション」を開催してくれており、私も参加している。このセッションは録画され、毎回ユーチューブで世界に配信されている。
和尚は「この宇宙で起こるすべての現象の中で最大の奇跡は師と弟子の出会いだ」と述べている。人生において縁友との邂逅ほど意義深いことはないであろう。竹内まりやの「命の歌」では「この星の片隅で、めぐり会えた奇跡は、どんな宝石よりも、たいせつな宝物」と歌われているが、素晴らしい歌詞である。
華厳思想では「一即一切、一切即一」が語られているが、パンディ君との廊下での会話から展開したネパールとのご縁を振り返ってみる時、まことに一から一切が始まるのだと実感させられる。
2025/7/25

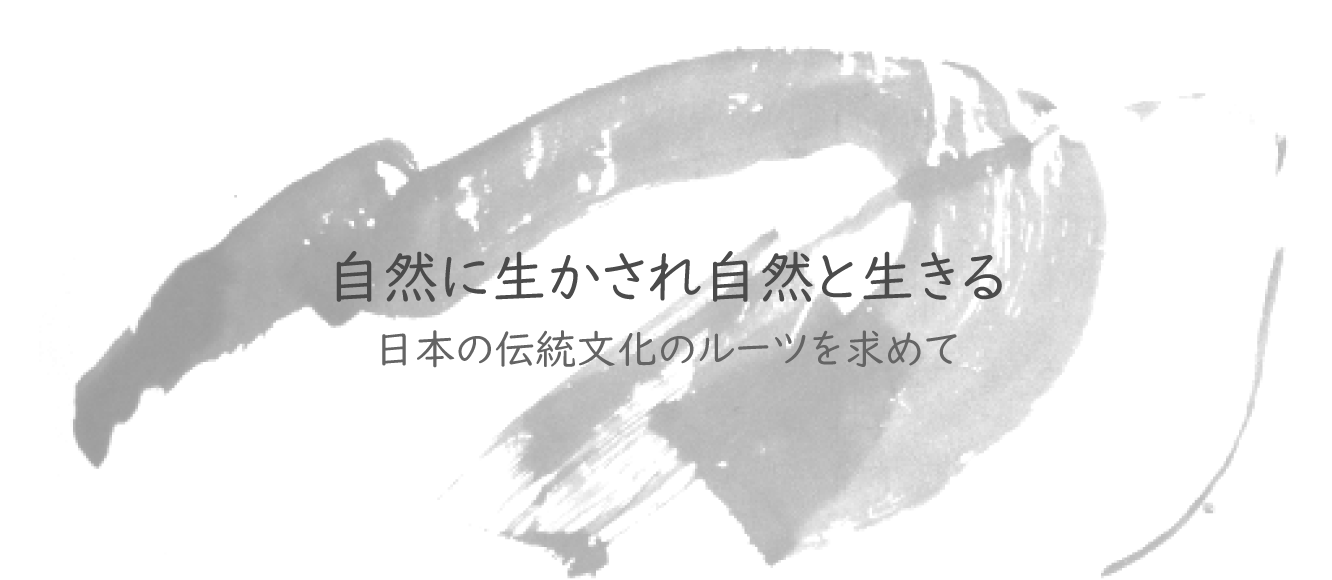
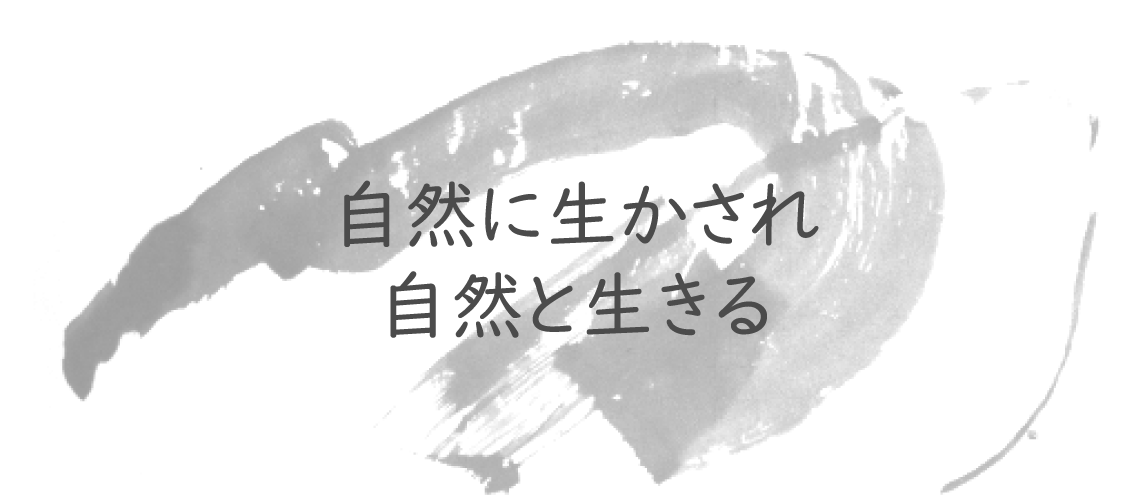
Comment
昔から、日本では、「袖すり合うも他生の縁」「縁は人には作れない」「縁ほど怖いものはない」といった「ご縁」についての言葉が伝えられています。
袖すり合うも他生の縁、「他生」の意味とは何か━。戦前まで、「輪廻転生」が、当たり前の日本の社会。他生とは、前世、来世のこと。つまり、袖がちょっと触れ合うだけの「ご縁」でも、前世からのつながりがあって初めて起きたこと。
同様、現在のつながりは、来世にまで続くもの。だから、大切に出会い、縁を育み、縁がはらんでいる可能性を花開かせて生きゆきましょうという先人の素晴らしい智慧である。
流水さんとのご縁も、今年で50年となる。どれほど多くの恩恵を頂いてきたことか、友との「ご縁」ほど素晴らしく価値のある豊かな宝はないと思っている。
私たち一人一人に託されているご縁が、花開くとき世界はどれほど豊かに、平和に、栄えることだろう。
そんな夢を見つつ、日本に生まれた幸せを感謝する。
永遠の生命を旅する私たちの魂が、この地球で再び巡り会えるのは、本当に奇跡のようなことだと思います。
流水さんとは、不思議な「ご縁」を感じています。60年来のソウルメイトであるAkiraさんの紹介で、2年前に初めてお会いしましたが、初対面なのにずっと昔から知っている人、という感じがしました。
言葉で会話しているのですが、まるでテレパシーを使って話しているかのように、相手のことがよく分かるのです。自分を飾ったり守ったりしようとする自我の壁が消えて、何の抵抗もなく話がすっと入ってゆく感じがしました。事務所でお会いしてから一緒に食事をしたのですが、気がつくと何と7時間も話し続けていました。
この人とは、どこかで一緒に修行したことがある、ぼんやりとそんな想いが心に浮かんできました。残念ながら、それがどんな時代で、どんな修行をしたのか、過去の転生の記憶は蘇ってきませんでしたが、私は、流水さんが一緒に道を求めるソウルメイトであることを確信しました。
そして、流水さんの「ご縁」は、私に新たな出会いを運んできてくれました。パンディさんやナムさんは、メールで毎月のNATURE通信と愚老庵の記事に、エールを送ってくださっています。機会が許すなら、ぜひリアルでもお会いしてみたいと思っています。
NATURE JAPANと愚老庵が結ぶ「縁生のネットワーク」が、これからどんな広がりと深まりを見せるのか、この星で巡り合う「縁の奇跡」を大切にしてゆきたいと思います。
コメント投稿には会員登録が必要です。