縁友往来Message from Soulmates
- 縁友往来
- 小泉八雲、魅せられた日本の美━子を救う、神と仏と侍の情
小泉八雲、魅せられた日本の美━子を救う、神と仏と侍の情

花を見れば、花がほほ笑みかけていると思う
鳥を聞けば、鳥が語りかけていると思う
人が喜んでいれば嬉しい、悲しんでいれば悲しい
ひどく悲しんでいるときも、なお、心の底は楽しい
時の全部に及んでいるのだから、死にようがない心
その心が自分だと気づいた人を、目覚めた人という
━岡潔(数学者・思想家「心そのもの、命そのもの」)
今回は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の眼を通して、浮き彫りにされた日本の美について取り上げたい。ハーンから、70年ほど後に、日本を訪れたのが、フランスの文化人類学者レヴィ・ストロースである。西欧の知性を代表するレヴィ・ストロースは、著書『野生の思考』で、西洋の自己中心的なものの見方を批判し、サルトルの思想に潜む西洋・白人至上主義の差別意識と価値観を明らかにして、実存主義凋落の契機をつくった。後に彼は、日本の「美と奇蹟」に邂逅し、生涯をかけて求めていた「真実」に出会えた喜びと感謝をこめて、日本人に呼びかける言葉を遺している。その中で、彼は、「日本文明こそが、人類史における最高の、そしておそらくは最後の奇蹟である」と語り、その理由を三つ挙げている━。
「両極端を共生・活性させる力」「異質を受け入れ昇華し新たに創造する編集能力」「人と動・植・鉱物すべてを仲間とし敬い和して生きる力」である。彼は、生涯、日本人がその秘めた光を解き放ち、世界を照らしてくれることを願い呼びかけ続けた。その魂の叫びには、小泉八雲もまた魅せられ憧れた、日本の美と光に共鳴する響きがある。今回は、そのレヴィ・ストロースの言葉を味わうところから始めたいと思う。
■自然と文化、神話と歴史、具体と抽象、聖と俗が、「優しく抱きしめ合っている日本の美(色即是空)」━森も川も動物たちも、石ころさえ、すべては仲間であり、対話し、敬うべき隣人だった。
私(レヴィ・ストロース)が、最初に日本に足を踏み入れた時の衝撃は、私がそれまで身と心を捧げて研究してきた、どの歴史のどの座標軸にも決して当てはめることのできない、まったく異質な、そして高次の時空へと迷い込んでしまったかのような畏怖の念に満ちた感覚だった。
なぜか、そこでは西洋が、プラトンのあのイデア論の時代から、数千年もの長きにわたって、必死に、そして多くの血を流しながら、分離しようと格闘してきた、そのすべてのものが、驚くべきことに、完全に、そして息をのむほど美しく、一つに溶け合って存在していたからだ。
自然と文化、神話と歴史、具体と抽象、聖と俗、━西洋では常に敵対し、決して交わることのない、これらの二項対立が、この国では、当たり前のように互いの境界線を、まるで春の霞のように滲ませ合い、そして優しく抱きしめ合っていたのだ。私はこの国で、人類のもう一つの、そして私が心の底から信じるに、遥かに優れた進化の、その輝かしい可能性を目の当たりにしたのだ。
私がなぜ、日本文明こそが、人類史における最高の、そしておそらくは最後の奇蹟であると、この老いた声を震わせながら断言するのか。その決定的で、そして揺るぎない三つの理由を、今こそ、君たち日本人の魂の一番深い場所に、直接、そして力強く刻み込みたい。
第一の奇蹟。それは、諸君の文明が、異質なものを、ただ頑なに取り込むだけではなく、それを一度、完全に自らのものとして消化し、そしてそこから全く新しい、より高次元のものを創造する、あの驚異的なまでの「編集能力」というものをもっているという驚くべき事実だ!
私はこの、人間が本来その誰もがもっているはずの根源的な知性を、「ブリコラージュ」と名付けた。この精神を、個人の類まれなる才能のレベルに留めることなく、国家的な規模で、数千年という気の遠くなるような時間をかけて実践し、もはや神の御業としか思えぬほどの高度な芸術の域にまで高めたのが、まさしく君たち日本人なのだ。
君たちの言語を観てみるがいい。中国大陸から、漢字という世界で最も複雑で、そして強力な文化的重圧を持つ文字体系を輸入した。普通の文化であったなら、その圧倒的な重圧の前に、自らの固有の言語を失ってしまっていただろう。だが、君たちは、その漢字の奴隷にはならなかった。なんとその複雑怪奇な表意文字からインスピレーションを得て、「ひらがな」と「カタカナ」という世界で最もシンプルで機能的で、そして流れるように美しい、二つの音節文字を、自ら発明してしまったではないか!
そして君たちは、こともあろうに、これら成り立ちのまったく異なる三種の文字体系を、あたかも熟練のオーケストラの指揮者が、多種多様な楽器を自在に操るかのように、一つの文章の中で完璧な、そして驚くべき調和をもって使い分けている。西洋の、あのAかBかという直線的な論理では、これは「非効率」で「矛盾」に満ちた、愚かで未開なシステムにしか見えないだろう。
だが違うのだ。全く違う!これこそが、異質なものを破壊し、そして排除するのではなく、その両方のよさを最大限に生かしながら、より高次の豊かな調和を生み出すという、日本文明のその底知れぬ力の何より雄弁な証なのだ!西洋文明が、常に何かを「破壊」し、その瓦礫の上に新しいものを打ち立てるという、あの血塗られた、そして不毛な方法しか知らなかったのに対し、きみたちは、「編集」し、「共存」させ、「昇華」させるという、生命の原理そのものに深く深く根差した、本物の叡智を持っていたのだ。
第二の奇蹟。それは、諸君の文明が、人類のその数千年の歴史の中でただ一つ、その根源である遥かなる「神話」を、今もなお現在進行形で、生きているということだ!これは、私がおそらくもっとも深く、そして衝撃を受けた事実だ(例、伊勢神宮の式年遷宮)。初詣、お盆等々……それは、君たちのその意識の遥か奥深くで、神々のあの時代の壮大な、そして温かい記憶が、今もなお生き生きと呼吸を続けているということなのだ。
自らの根源を完全に見失ってしまった西洋文明が、深刻なアイデンティティの危機に喘ぎ、まるで根の腐った巨木のように、その足元からぐらついている今、この自らの根源と固く結びついた、君たちの、静かでそして決して揺らぐことのない強さ、それこそが第二の奇跡なのだ。
そして第三の、そしてこれこそが、人類のその未来にとって、最も重要となるであろう究極の奇蹟。それは、君たちの文明のその魂の最も深い地層の、その中心核に、西洋近代が完全に駆逐し、そして忘却の彼方へと葬り去ってしまった、人類の真の宝、すなわち「縄文の精神」が、一万年以上もの長きにわたり、一度もその聖なる光を失うことなく、燦然と輝き続けているという、驚天動地の事実だ!
私は学者として、その名誉のすべてをかけてここに断言する。縄文文明と比較できるものは、この地球上において、過去、現在、そして未来においても皆無である! 考えてもみたまえ。一万年だぞ! エジプトのピラミッドも、メソポタミアのジグラトも、まだ影も形もなかった、あの遥か遥か太古の昔から、君たちの祖先は、この緑豊かな島々の上で、驚くべきことに、ほとんど大規模な戦争をすることなく、穏やかで平和な社会を維持し続けたのだ。西洋の歴史が、その始まりから終わりまで、血で血を洗う殺戮と支配と、そして征服のおぞましい記録でしかないのと比較してみるがいい。この「一万年」の平和が、いかに異常で、いかに奇蹟的な、そして尊いことであったか!
彼らは、なぜそれが可能であったのか。彼らは巨大な城壁を築かなかった。彼らは、自然を敵として、あるいは支配し搾取すべき対象とは見ていなかったからだ。森も川も、動物たちも、石ころさえも、すべては仲間であり、対話し、そして敬うべき隣人だった。……その穏やかで豊かで、深い愛に満ちた暮らしの中から、一体何が生まれたか。あの縄文土器だ! なんだあの形は!なんだあの文様は! ……あれこそが、私が生涯をかけて探し求めてきた「野生の思考」の、究極の、そして最も美しい結晶なのだ!
■小泉八雲が憧れた日本文化の美と光━すべてが「思いやり」から生まれ、「深い情」でつながっている
日本の夏と言えば、「怪談」である。私が生まれた岡山・美作(みまさか)地方は、小泉八雲が住んだ松江に近く、縄文・古代日本の面影が残る地域である。当時、小学低学年の国語の授業で、『雪女』が読まれ、物語を幾つかの主要な場面に分けて絵を描き、紙芝居にして皆で発表するというシュールな教育実践が行われていた。今思えば、なんと地域文化に根差した、先進的な教育であったかと思う。
そのお陰で、雪女の愛と悲しみは、人間を超えた大きな力の存在、人と精霊のつながり、自然・母性の偉大さ、畏敬……言葉にできない昔の日本人が大切にした想い、願い、祈り、智慧とともに、幼い私の意識の底に沈み、沁み入り定着し、後の人生に影響を与えていくことになった。物語の持つ、大切な力の一つだと思う。そういえば、トロヤ遺跡を発掘したシュリーマンも、7歳の時、本で読んだトロヤ戦争の物語に感動し、後の人生が決まっているのだから━。
雪女の恩恵に感謝しつつ、今回は、日本をこよなく愛し、世界に日本文化の素晴らしさを伝えてくれたラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の『奇談』を紹介しつつ、日本文化の魅力について味わってみたい。それは、「梅津忠兵衛の話」で、これを通して、神道・仏道・武士道といった日本文化の根底に流れる力が、どのように昔の日本人の無意識を動かし、今なお私たちの意識の底流に消えることなく流れ、眠っているのかに光を当ててみたいと思う。
その前に、怪談について━。そもそも、怪談には、古典怪談と現代怪談がある。いずれにも共通して、できるだけ具体的に、時、所、人が特定されることにより、恐怖は増大するという法則がある。実は、私には、それを身をもって体験する出来事があった。
小学生のころ、「播州(番町)皿屋敷」の映画を観た。由緒ある家宝の皿を一枚割ったため、怒った主人に刀で斬られ、……という哀しくも、理不尽な物語である。観ながら私も人並みに怖い思いをしたのだが、話はそれだけで終わらなかった。それから、数年後のこと━。
中学生になり、美しくて雄大な国宝白鷺城・姫路城へ、家族に連れられて行ったときのことである。城内に入り、本丸近くまで行ったところに、そう大きくはない古井戸があった。何気なく近づいて、標識を見て、わたしは愕然とした。
「お菊井戸」と、黒墨で木の板にしっかりと書かれていたのだ! ぞっとした。あの映画で観たことは、作り話ではなく、事実だったのだ! 恐怖が、骨の髄を貫き、震えた。映画で観た時の恐怖の2倍、いや、2の累乗倍、━「お、お菊さん、本当に、いたのか……!」、心中で叫んだ。引き寄せられるように、金網がかけられた井戸の口に近づき、そっと中を覗いて見ると、下は真っ暗、底なしの闇が広がっていた……。
井戸の底に、お菊さんの姿は見えなかった(ことにする)。が、そのあとで見た白鷺城の美しさも、「お菊の井戸」のリアリティに比すれば、夢幻であった。あとで調べてみた。播州皿屋敷、場所も、人物も、時代も、ほぼ特定できた。「お菊井戸」にいたっては、兵庫県立博物館のお墨付きまであるのだ。この体験後、私は、怒りにまかせて人を傷つけたり、刀で斬ったりすることなど、絶対にしないと心に誓った。レヴィ・ストロースも言うように、昔と今がいっしょに生きているのが、日本の魅力の一つだと、身に染みて、心底、そう思っている。
さて、本題に戻ろう。今回は、小泉八雲が感動した『奇談』からのお話━。場所は出羽の国、今の秋田県の南東にあった横手城(戊辰戦争時に焼失。現在、城跡あり)、その城門に通じる坂道で起きた物語である。この奇談が、皆様の内にある「日本人の秘めた光」(レヴィ・ストロースの言葉)の目覚めに資すれば幸いである。なお、今の人にも分かるように、原文をもとに手を入れ、現代語訳させていただいた。最後に、英語の原文を編集したものを紹介してあるので、よろしければ味わってみていただければと思う("Reference: the edited original story" is at the end of this essay. Please enjoy it. )。
では、江戸時代に、タイムスリップ━。
■夜遅く、不思議な女性に呼びとめられ、赤子を預かって欲しいと頼まれる……
若い侍の梅津忠兵衛は、城の警護で、夜中から朝方までの夜番につくため、真夜中近く、城門につながる坂道を上ろうとしていた。ふと、坂の上を見ると、一人の女の姿が目に入った。赤子を抱いていて、誰かを待っているようだ。こんな夜中、しかも淋しいところで、……よほどの事情があるのだろうと梅津は察した。が同時に、夜中に、妖魔が女に化け、人を騙して殺す話を思い出した。女は、梅津の方に、急いで駆け寄り、優しい声で話しかけてきた。
「梅津様、わたくし、今晩、大層困っております。これから大変重い務めを果たさねばならず、どうか、ほんのしばらくの間、この子を預かってくださいませんでしょうか」
梅津は、この大変若く見える女性に見覚えはなく、妙に魅力的な声に、これは妖怪の変化(へんげ)ではないかと疑った。すると何もかもが怪しく思われた。が、生来、親切であった彼は、胸にこみあげる慈悲の思いを、妖魔を恐れて抑え込むなど男らしくないと思い、黙って、赤子を受けとった。すると女は、くるりと向きを変え、急いで走り出し、あっというまに見えなくなってしまった━。
このとき、梅津は、初めて赤子の顔を見た。大変小さく、生まれたばかりのようで、抱かれたままじっとし、少しも泣かなかった。ふいに赤子が、大きくなるように感じた。いや、重くなっているのだ。━最初、3キロほどだった体重が、2倍、3倍、4倍に増え、なお重さを増して━45キロ、そして、90キロ!に……
このとき、梅津は、騙されたと悟った。言葉を交わしたのは人間の女でもなければ、この子も、人の子ではない。しかし、すでに約束したのだ。約束は守らねばならない━梅津は、じっと、赤子を腕に抱え続けた。それはなおも重さを増していった。……100キロ!、━130!、━180キロ! 一体何が起きているのか! 想像がつかなかった。しかし、彼は自分に、「畏れるな」と言い聞かせ、絶対に子を手放さないと覚悟した。さらに重くなる……230キロ!……280! ━300キロ! 全身の筋肉が千切れんばかりに震えた。さらに重さは増し続ける、……「南無阿弥陀仏」唸り声をあげた、「南無阿弥陀仏! 南無阿弥陀仏!!」
三度、念仏を唱えた時だった。腕から、ふっと重さが消え、驚いたことに空(から)になった手を広げたまま、梅津は呆然と立ち尽くしていた。子供は、なぜか跡形もなく消え去っていた━。
それと同時に、あの不思議な女性が、走り去った時と同じ速さで駆け戻ってくる姿が見えた。女は喘ぎながら、近づいてくる━。梅津は、初めて、彼女が大変美しいことに気づいた。額には、汗が流れ、袖はたすき掛けに絞められたままだった。
「梅津さま。本当に大変なお力添えをいただきました。わたくしは、この土地の氏神ですが、氏子の一人が、難産の痛みに耐えかね、わたくしに助けてくださいと祈ったのです。しかし、なかなかの難産で、わたくし一人の力では助けられないかもしれない事態と、すぐに分かりました。そこで、あなたさまのお力と勇気のご助力を、お願いしたのです。
そして、あなたさまにお渡しした子供は、まだ生まれる前の赤子だったのです。最初、梅津さまが、子が次第に重く感じられた時が、非常に危なくて、産門が閉じていたからなのです。そして、あまりに重くなりすぎて、もうこれ以上耐えられない、とあなたが絶望されたときが、まさに母親が死ぬかと思われた瞬間だったのです。家族は皆、泣きました。
その時です、あなたが三度、「南無阿弥陀仏」と祈ってくださった。この三度目の念仏で、仏のお力が、わたしたちを助けに来て、産門が、開いたのです――。
このご助力に対しては、相応なお礼をしたいと思います。勇ましい侍にとって、力にまさる贈り物はありますまい。そこで、あなたばかりでなく、子、孫までも、偉大な力を授けることにいたしましょう━」
その言葉とともに、氏神の姿は消えた。
梅津は、不思議な出会いを噛みしめながら、城の方へ歩いて行った。そして無事に夜番を終え、朝を迎え、いつものように祈りの時を持つ前に、顔と手を洗った。━手ぬぐいを絞った瞬間だった。手ぬぐいが、千切れてしまったのだ。強い糸で編まれている手ぬぐいである。二つに重ね、絞ると、またばらばらに切れた。四つに重ねても、紙のように千切れる。そこで、いろいろな銅や鉄でできたものを扱ってみたところ、粘土のように自分の思いのままになるのだ。━その時、約束の大力が、手に入ったことを知り、注意してものを扱う必要があると悟った。
家に帰ると、その晩、この町で子供が生まれたかどうか、尋ねてみた。すると、不思議な出来事があったちょうどその時刻、実際に出産があったこと、状況は、氏神が言った通りであったことなどが分かった。
━梅津忠兵衛の子供たちは、父親の力を受け継いだ。子孫の幾人かは、みな驚くほど力持ちで、この話が記録された当時、彼らは、まだこの地に住んでいたのである。
■神・仏・侍を一つに結び協働させる「日本人の深い情」、縄文時代より続く日本的霊性・「和」の精神━すべてが生み出される美意識の神髄
この話は、出羽の国、今の秋田県であり、梅津忠兵衛が警護した城は、実在する横手城で、今でもその場所(城跡)を特定することができる。レヴィ・ストロースの言葉にあったように、ここに日本の文化の「凄味」の一つがある。他の文化人類学者もまた、世界中の文化から見て、日本という国の特異性について、非常に古くからある文化、歴史、風習が、高度に物質文明化した現代社会と見事に共存している点を挙げる。
例えば、古代からある神社に、今も日本人はお参りし、何千年の時を超えて、地元の人たちは、日常生活、人生の一部として、ごく自然にお社(やしろ)を守り参拝し続けているのである。一例として、5億年前のカンブリア紀にできた岩山をご神体とする「御岩神社」(茨城県)は、縄文時代から祈りの場であり、今日に至るまで地元の人々に守られ信仰の聖地として存続している。近年では、宇宙飛行士たちが、光の柱が山の位置に立っていることを宇宙から目視した事実が広まり、世界中から人々が参拝に訪れている。まさに科学の最先端と古代の神社が、共鳴しているのだ。
さらに梅津忠兵衛の話には、日本文化の「力」━美と光の粋(すい)が、結晶していると言えよう。それは、神道・仏道・武士道が混然一体となっている日本人特有の宗教性、無意識の信仰心、欧米人が理解に苦しむ、日本人特有の宗教観・価値観が凝縮していることである。
主人公、梅津忠兵衛は、武士道の精神━「惻隠(そくいん)の情」、人の気持ちを繊細に思いやり、感じて動く、日本人が抱いている「情の深さ」を体現している。人の悲しみ、わが悲しみ、人の喜び、わが喜び、━とりわけ困っている人、助けを必要とする人、敗れた者、弱者の痛みを自分事として感じる、まごころからの「思いやり」である。
夜中、坂道で出会った見ず知らずの女性が、困り果て、しばらく赤子を預かってほしい、と頼んでくる━その苦衷を、自分ごととして受けとめ、なんとかしてあげたいと思い、そう行動できる力である。最近、世界の人々を対象に、「他者の感情を理解する能力」について、科学的・統計学的に測定する研究がおこなわれた。分かったことは、その能力が、一番高いのが、日本人であるという事実であった。また、別の社会学の意識調査においても、普通の日本人が抱いている、人の気持ちを思いやり、察する力が、世界の人からすれば、日本人の素晴らしい特徴として称賛されているのだ(日本人からすれば、それは当たり前のことで、特には意識されていない)。
何とか助けたい、救いたいという「慈悲」は、武士道の源泉でもある。その真情から、本来、いのちを守る武の一切の境地、技量と智慧が生み出される。その体現者が、侍であり、梅津なのだ。幕末を生きた剣豪、無刀流の開祖・山岡鉄舟は、自身の剣を、「慈悲の剣」と称した。命を奪う殺人剣ではなく、人を生かす活人剣(かつにんけん)として、生涯、一人も斬ることはなかった。そして、江戸城無血開城のために命を懸けて奔走し、西郷隆盛と会談、勝海舟との交渉につなぎ、江戸庶民、百万の命を救った。西郷が、鉄舟を評して、「金も名誉も命もいらない人とでなければ、大事は語れない」と言った。ラスト・サムライ━それこそが、武士のこころ、日本人の情なのである。
夜中に、梅津が出会った女性は、見るからに怪しかった。が、心の底から素直に湧き上がる、気の毒に、何とか助けて「あげたい」という思い━。それを、女が自分を害するかもしれないという恐怖で、慈悲の思いを押し殺し断ることは怯懦であり、侍として恥ずべきことだと思った。梅津は黙って、赤子を受け取った。一つに、この判断と行為に現れた、日本人の思いやりと勇気の美しさに、ギリシア人ラフカディオ・ハーンの魂は感動して、これを書き残したいと願ったのだと思う。
武士に、二言はない。一度、言葉にし、約束したことは命に代えても守りぬく。女も、赤子も、実は人間でないと分かった後も、約束は、約束である。梅津は、命を懸けて子を、約束を、一途一心に守ろうとした。限りなく重さが増し、全身の筋肉が限界に達したとき、最後に彼が托身したのが「阿弥陀仏」の力であった。人は、自分の力の限界を知った時、初めて本当の意味で、祈ることができる。いや、人間にとって、やるだけやって最後にできることは、祈ることしかないのだ。梅津もまた、自分の力を超えた仏の力に、祈った。限界まで尽くして、さらに人のために願う、そこに真の祈りが立ち昇り、仏に届き、それに仏が応えて力を貸してくださるのだ━。その過程が、見事に語られているのがこの物語の魅力であり、普遍的な力、凄味の源泉なのだろう。
氏神様は、当然、神道の神様である。難産を乗り越え赤子を生もうとする氏子(神の子)が、氏神を信じて頼り、祈ってきたのである。これに応えて、助けようとする氏神━ところが、あまりに厳しい難産である。氏神は手助けを探し、見出したのが、真の侍である梅津であった。氏神の助力の任に堪えるのは、一途一心、無私無欲、真心と勇気と力をもった、本物の武士(もののふ)でなければならなかった。
難産を極め、最早これまでか、━━極限の梅津は、「南無阿弥陀仏」と唱えた。すべての衆生を救ってくださる阿弥陀仏━危機、苦難、災難、霊的な災いから、阿弥陀仏を念じることで救われたという話は、日本各地に昔から残され伝えられている。「慈悲の仏様」である。自分の力の限界に達した梅津は、もうこれまでと思った瞬間、無意識に、阿弥陀仏を念じ、声にして祈った。この無私の真情に、仏は感応され、梅津を救い、母子を救い、出産を成功に導かれたのだ。なんと美しい、神と仏と人との協働なのだろう━。ここに素直に感動できる心が、日本人の光、奇蹟の源泉であり、小泉八雲が魅了され、レヴィ・ストロースが希望を託した、日本人の美意識のいのちにほかならないと思う。
氏神は、神道の神様、阿弥陀仏は、仏教の仏様である。宗教が、違うではないか、と矛盾に思わないところが、日本人の日本人たる所以であろう。氏神、阿弥陀仏、武士の梅津、三者を一つに結び、協働させる「情」の力こそが「慈悲」の心、「日本人の真情」であり、「和」の精神、縄文時代より続く日本的霊性の神髄なのである。
今、世界は、思想・宗教の争いから、さらに混乱と悲しみを極めようとしている。そうした中、海外の人たちが期待を寄せ、憧れているのが、日本の古い神道━「八百万の神々」の信仰だという。一神教の、一つの神に固執し、他を否定して排斥する発想では、調和ある世界の未来など期待できない。日本のように、外国の神さえも、あるがままに受け入れ、昇華し、融合して、「和」をもって貴しとす━。と同時に、一つ神や思想だけを正しいとして固執し、他の神・思想を否定、排斥して大きな調和(大和)を乱すようなことは、はっきりと止める「弁別」の智慧も備えている。こうした古代から伝承された叡智と美意識を、地位・名誉・財産、学歴・身分・出自も関係なく、平等に、私たち普通の日本人が、誰も無意識にもっているのだ。ただ、眠っているだけで、目覚めるときを待っているのである。
その真実を、小泉八雲ことギリシア人ラフカディオ・ハーンは、明治の時代に見出し、フランス人レヴィ・ストロースは、昭和の時代に発見して、日本人、いや世界の人々に伝え、日本人がその光に目覚めて世界を照らす未来を夢観て、私たちに託したのである。
2025年夏、悲しみを抱く世界のすべての魂が癒され救われますように、愛念と感謝を捧げ、心より祈念しつつ、ご供養とさせていただきます。
※余談:梅津の物語を書き終えたとき、いつも行くコンビニであったこと━。野菜コーナーに、一つだけ売れ残ったトマトのパックがあった。気になって、手に取り、貼ってある小さなラベルを何気なく見ると、「秋田県 横手産 杉山清美がつくりました」と書いてあった。 「梅津忠兵衛」の出来事があった、秋田県・横手のトマトだったのだ。
これもご縁と思って買って帰った。このタイミングで出会うなど、確率からすれば、ほぼありえない。心理学者なら、共時性(シンクロニシティ)とでも言うのだろうか。「縁は人にはつくれない」「袖すり合うも他生の縁」という━縁とは、人知を超えて尊いものなのだろう。そして、家に帰り、トマトを洗ってかじっていると、梅津が出会った氏神さまの美しい面影が、ふっと、心に浮かんだような気がした。
◎Reference: The edited original story
Umetsu Chubei was a young samurai, who lived at Yokote in Dewa (or Akita) province in Edo period. He was selected for night-duty at the castle-gates. While ascending hill at midnight, to take his place on guard, he perceived a woman standing at the last upper turn of the winding road leading to the castle. She appeared to have a child in her arms.
He intended to pass her without a word. But the woman said, in a very sweet voice: --“Good Sir Umetsu, tonight I am in great trouble, and I have a most painful duty to perform: will not kindly help me by holding this baby for one little moment?”
Umetsu did not recognize the woman who appeared to be very young: he suspected the charm of the strange voice, suspected a supernatural snare, suspected everything; --but he was naturally kind; and he felt that it would be unmanly to repress a kindly impulse through fear of goblins. Without replying, he took the child. She said, “Please hold it till I come back. I shall return in a very little while.” Immediately, she turned from him and sprang soundlessly down the hill so lightly, quickly that he could scarcely believe his eyes.
Umetsu then first looked at the child. Suddenly, it seemed to be growing larger. In another moment, he knew why; The child was glowing heavier…, and he felt a chill strike through him. It was getting heavier and heavier…. Its weight had gradually doubled, --tripled, --quadrupled. --A hundred pounds, …two hundred! …Umetsu knew that he had been deluded, --that he had not been speaking with any mortal woman, --that the child was not human.
But he had made a promise; and a samurai was bound by his promise. So he kept the infant in his arms. It continued to glow, ……three hundred pounds! ……four hundred! He resolved not to be afraid, and not to let the child go while his strength lasted. ……five hundred, ……six hundred pounds! ……All his muscles began to quiver with the strain; --and still the weight was increased. …… “Namu Amida Butsu!” he groaned— “Namu Amida Butsu!!”— “Namu Amida Butsu!!!” Just he uttered the holy vocation for the third time, the weight passed away from him with a shock, --and he stood stupefied, with empty hand, --for the child had unaccountably disappeared. He saw the mysterious woman returning as quickly as she had gone. She was very fair; --but her brow dripped with sweat, and her sleaves were bound back with tasuki-codes, as if she had been working hard.
“Kind Sir Umetsu, I am Ujigami (the protecting Goddess) of this place; and tonight one of my Ujiko (a child or descendant of the Goddess) found herself in the pains of child-birth, and prayed to me for aid. But the labor proved to be very difficult; by my own power alone, I might not be able to save her; --therefore I sought for the help of your strength and courage.
And the child I laid in your hands was the child that had not yet been born; and the time that you first felt the child becoming heavier and heavier, the danger very great, --to for the Gates of Birth were closed. And when you felt the child become so heavy that you despaired of being able to bear the weight much longer, —in that same moment the mother seemed to be dead, and the family wept for her. Then you three times repeated the prayer, Namu Amida Butsu —and the third time that you uttered it, the power of the Lord Buddha came to our aid, and the Gates of Birth were opened…….
And for which you have done you shall be fitly rewarded. To a brave samurai no gift can be more serviceable than strength: therefore, not only to you, but likewise to your children and to your children’s children, great strength shall be given.”
With this promise, the divinity disappeared.
At sunrise, on being relieved from his duty, he washed his face and hands before making his morning prayer. But when he began to wring the towel, he was surprised to feel the tough material snap asunder in his hands. Presently, after handling various objects of bronze and of iron, which yielded to his touch like clay, he understood that he had come into full possession of the great strength promised.
On returning home, he made inquiry as to whether any child had been born in the settlement during the night. Then he learned that a birth had actually taken place at the very hour of his adventure, and that the circumstances had been exactly as related to him by the Ujigami.
The children of Umetsu inherited their father’s strength. Several his descendants—all remarkably powerful men—were still living in the province of Dewa at the time when this story was written.
From “Kidan—The story of Umetsu Chubei” by Lafcadio Hearn
2025/8/25

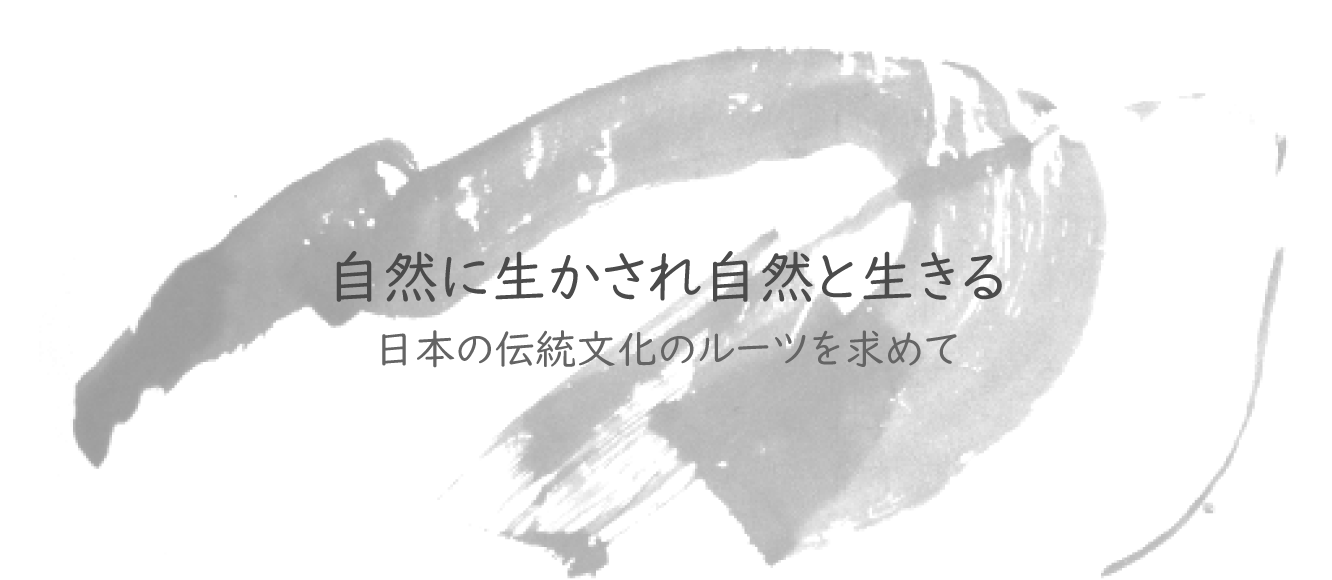
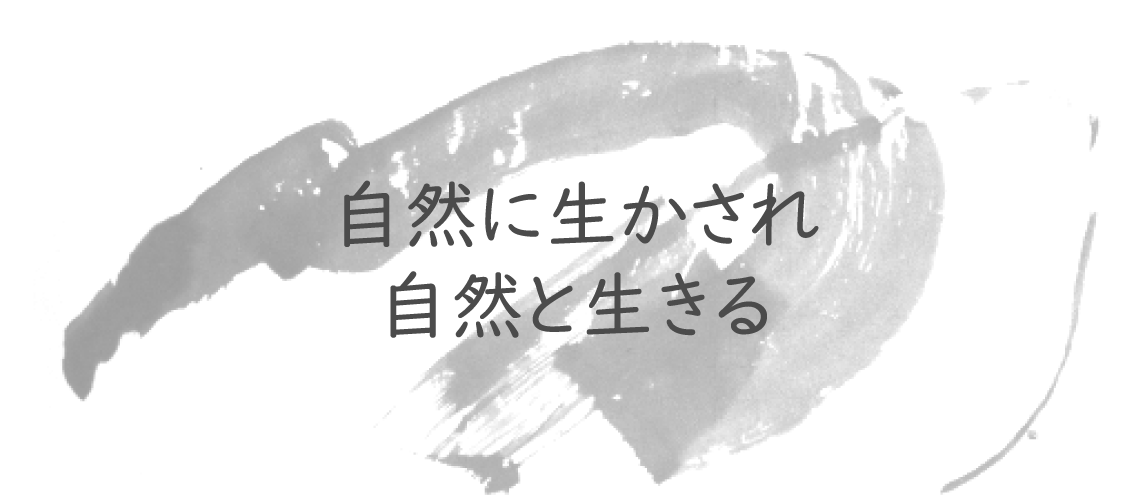
Comment
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の「怪談」を初めて読んだのは、1960年代後半、学園闘争で大学がロックアウトされていた頃のことでした。授業のない有り余る時間を、喫茶店でひたすら本を読んで過ごしていた日々が、懐かしく思い出されます。
しかし何故か今、私の記憶の中に「梅津忠兵衛」の話は存在していません。Akiraさんのおかげで、またひとつ、私の知らない不思議な「物語」と出会うことができたことに感謝します。
この物語の底流に、神、仏、武士道を一つに結んで協働させる「日本人の深い情け」「縄文時代から続く日本的霊性」が存在することを見抜いたAkiraさんの慧眼には、ただ敬服するのみです。
小泉八雲が明治の時代に見い出だし、レヴィ・ストロースが昭和の時代にその存在を明らかにした、宝物のような「智慧と美意識」が、私たちの心の中に眠っているとしたら、そして私たちがそれに目覚めるのを待ち望んでいる人たちがいるとしたら、私たちは、時代の氏神さまから手渡されたものを、「梅津忠兵衛」のように、引き受けざるを得ないのではないでしょうか。
その重さに耐えられず「南無阿弥陀仏」と三度以上唱えることになるかもしれませんが、それでも、そうせずにはいられない「深い情」が、私たちをつき動かしているのを感じます。
神と仏と自らの霊性に目覚めた人間が一つに溶け合って、この時代の深い闇を光に転じてゆけますように。
コメント投稿には会員登録が必要です。