縁友往来Message from Soulmates
- 縁友往来
- 本草学の魅力
本草学の魅力

茨城大学に赴任して10年ぐらいたった頃、牛久愛和総合病院の院長の高崎健先生から突然会いたいとの連絡を頂いた。高崎先生は東京女子医大名誉教授で日本を代表する消化器外科の権威である。わざわざ茨大までお越し頂き、お話を伺った。先生からまず言われたことは、「茨城県は都府県でもトップの農業生産額を誇る農業県なのに、どうして食のリテラシーに取り組まないのか」との質問だった。
先生は、消化器外科医として毎日消化器癌の摘出手術を行ってきたが、切っても切ってもキリがなく、限界を感じるようになったそうである。もっと根本的な見直しの必要性を痛感し、食による癌予防を考えるようになったと語られた。最近では日中医療交流事業で中国を頻繁に訪問され、中医学の「医食同源」の健康観に共感するようになったとのことだった。
農学部の教員として食と健康には関心があったが、専門が農業経済学であったこともあり、食のリテラシーを自分の研究対象として考えたことはなかった。高崎先生のお話を伺って初めて、食のリテラシーの大切さに気付かされた。
ちょうどその頃、中国からの留学生の王大超君と知り合った。王君は本草学の素養があり、彼を通じて本草学(中医学)に触れることになった。当時、私は毎年花粉症に苦しんでいたのだが、王君が処方してくれた薬草茶を飲んだところ、花粉症が治る経験をした。菊花(キクカ)、紅花(ベニバナ)、金銀花(キンギンカ)、陳皮(チンピ)、大棗(タイソウ)、訶子(カシ)などの一般的な生薬を処方してくれたのだが、10日間ぐらいで症状が軽減し、1カ月ぐらいでほぼ治ってしまった。このことが、本草学への関心をさらに高めることになった。
丸亀高校同窓会で再会した大阪大准教授の高橋京子さんが、確か本草学を研究していたことを想い出して、高橋さんに連絡して、本草学の話を聞くことにした。王大超君と殷佩揄さんを連れて車で大阪大を訪問し、初めて大学の薬草園を見せてもらった。
高橋さんからは金沢大学の御影雅幸先生や国立医薬品食品衛生研究所の柴田敏郎先生を紹介してもらった。富山大や金沢大の薬草園も見学することができた。折角の機会なので、高崎先生、高橋先生、御影先生、柴田先生にも参加してもらって「アグリセラピー(農業療法)の開発」で科研費を申請し、僅かだが研究費も確保した。私の研究室は柳島宏治先生にも手伝ってもらい、主に食と健康の関係の統計分析を担当した。
AGRI事務局長の中村耕二郎先生も本草学には興味を持たれ、中国語が読める先生は中国から本草学の古典を取り寄せて読み始められた。まず附属農場で圃場を借りて主要な生薬やハーブをすべて栽培してみようということになった。このことにより、ユウカリが3年で高木になること、棗(ナツメ)の木も成長が早く、ただ鋭い棘の取り扱いが大変であること、甘草(カンゾウ)は土壌条件さえ整えてやれば1年で2m以上も根を伸ばすことなどを体験した。一般に薬草は生命力が旺盛である。厳しい環境に耐えて成長する過程で人体に有用な薬効成分が生産される。
本草学は、食養生、鍼灸、按摩から構成されている。食養生については、人間が口にするものは全て薬であると考える。全ての食物を、五味(酸、苦、甘、辛、鹹)、五気(熱、温、平、涼、寒)、帰経(肝、心、脾、肺、腎、胆、小腸、胃、大腸、膀胱)の視点から分類している。
患者の特性やその時の状態を見て、陰陽・五行(木・火・土・金・水)理論から食物の組み合わせや配分量を決めて、治療や養生を図っていく。個々の患者の症状に応じたオーダー・メイドの療法である。
高校生の頃、夏休みや冬休みに斎藤眞諦老師と剣山で修行をしていたが、剣山に棲息しているどの野草を尋ねても老師は即座にその名前と食べられるかどうか、食べられる場合にはその薬効は何かを教えてくれた。老師はどうしてすべての野草についてこんなに詳しく知っているのか不思議に思ったが、今振り返ってみると、老師は本草学を極めていたのだと思う。
一度「先生は、鍼灸や整体のことを知っていますか」と尋ねたことがある。老師の答えは「私は、鍼灸師や整体師の先生だ」というものであった。どこまで書いていいのか悩ましいのだが、老師の治療に何度か同席したことがある。
中学の同級生のA君は、胃のあたりがチクチク痛いと訴えていた。胃のレントゲンを撮ったが、異常は見つからなかった。このことを老師に尋ねてみたら、即座に彼の場合は胃の外側に腫瘍ができているとの答えだった。前回彼に会った時にどうしてそのことを教えなかったのか尋ねてみると、聞かれるまでは答えないとのことだった。老師から市販の漢方薬を教えてもらい、A君の胃の痛みは解消した。
ある初老の女性が、足先の感覚が麻痺してきたことを訴えた。老師は少し症状を見て、すぐに過去に流産したことがないか尋ねた。妊娠、出産は自然な現象だが、途中で流産すると一部の微細な神経が切れてしまい、晩年にその様な症状が出てくるのだそうだ。
仏教では信学行(信仰・学問・修行)が進むと神通力が出てくると説かれている。信学行を極めた老師には、どうも患者の経絡の気の流れや前世の姿が幾重にも見えていたらしい。本草学も脈診や望診、鍼灸などを極めるとこの境地に至るらしい。
チベット仏教では、顕教の修行が一通り修了して微細な煩悩である細妄執、極細妄執も抜けると、選ばれて密教学堂に進学する。密教学堂では修行者は天文学と医学を学ぶ。今でも医学はチベット密教の重要な柱となっている。
近代は “divide and rule”(部分に分割して管理する)を特徴として生産力を急速に拡大させてきた。科学の発展もこの傾向を強めてきた。東大の薬学部の教育カリキュラムなどを見ると、最近では有機化学と分子生物学が主体となっており、解剖学は学ばず、薬剤師の育成教育も軽視されている。早く創薬研究者を育成するという時代の要請に答えるためにはいたしかたない趨勢なのかも知れないが、生命の全一性は無視されている。
本草学は、生態学的でホリスティックな学問である。行き過ぎた近代の “divide and rule” の潮流を是正し、生命の全一的機能を回復させる可能性を秘めていると思う。
2025/8/25

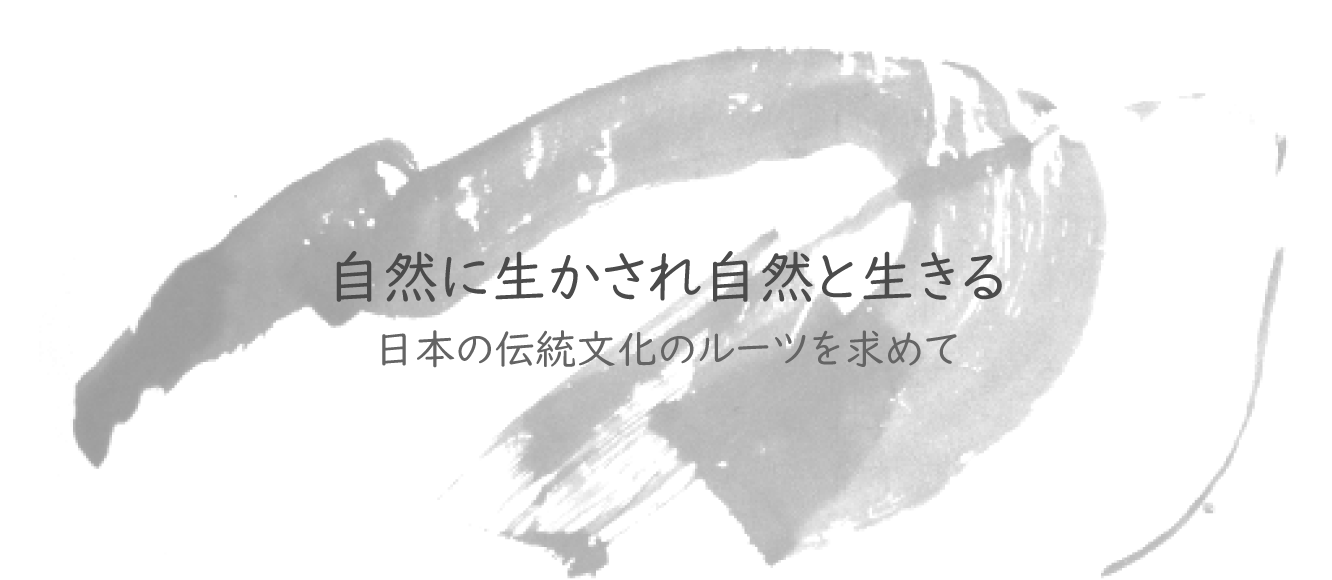
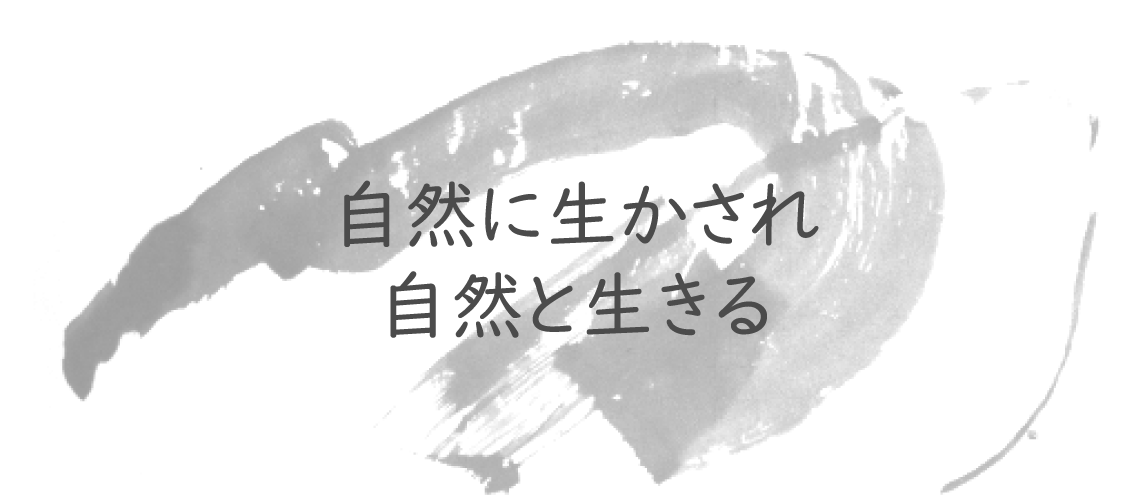
Comment
エッセイ「本草学の魅力」を拝読し、以下、荘子の一説を思い出しました。
どんな重病患者でも治すという、有名な名医を訪れた。その医者は、「私など及びもつかない名医がいる。その方は早期治療の権威で、大病になる前に治す大家だ」という。その大家を訪れると、「私など及びもつかない名医がいる。彼は、病気になる前に未病の段階で治す。彼こそが、本物の名医の中の名医である」という。
早速、その名医中の名医を訪れると、何とも貧しく、誰も彼が名医であることなど知らない。分かったことは、病になる前にみんな治してしまうので、まったく儲からないし、評判にさえなりようがなかったのだ、という話である。
ブッダのことを、本当の病、病の根源を治す人という意味で「医王(いおう)」とも呼ぶそうだ。現代医学で、病の原因を突き詰めると、結局、体も病も作っている「食」に行き当たる。「食」が見直され世界的に注目される時代になった。
欧米で、癌は減少しているのに、日本だけ増え続けている主な理由が、「食」(添加物など欧米に比して多量に摂取)にあるという見方がある。その通りだと思う。「食」から、さらに病の原因を遡れば、「心(気持ちの持ち方)」にある。そこまで、現代医学は追いついてきている。しかし、流水氏が指摘するように、「生命の全一性」に立つ、ホリステックな医療は、まだまだ遅れている。
高次は低次の法則を支配し、影響を与え、変えてゆく。循環の法則によれば、心の健康→食の健康→体の健康→生の健康→全的幸福。まずは、心が健康でないと、食も、体も、健康ではいられない。苦しみを抜き楽を与えるブッダが、医王と称される所以だろう。
今、日本で暮らす私たちは、人類史上稀に見る「飽食の時代」を謳歌しているのではないでしょうか。
食料品店の店頭には世界中から集められた食材が溢れ、飲食店は豊富なメニューを揃えて、料理やスイーツの美味しさを競い合っています。しかし、美味しいものを好きなだけ食べられるという、この願ってもない環境が様々な「病気」をつくり出している、そう言われる時代がやってきました。
「性欲」は、法律や社会の暗黙のルールによって抑制されていますが、「食欲」にはタブーがありません。私たちは、誰にも邪魔されず、罪の意識を感じることもなく「食べる自由」を謳歌することができます。しかし、その結果については、自分の体で自己責任を負わなければなりません。
街やメディアに溢れる「美味しい誘惑」に乗って飽くなき食欲に身を委ねるのか、健康やQOLを考えて「医食同源」の道を行くのか、私たちは今、食の世界で「自由意志」の選択を迫られているような気がします。
流水さんのエッセイを拝読しているうちに、大学を卒業して就職した直後、新入社員研修で鎌倉の「禅寺」に1週間、缶詰になったことを思い出しました。
朝食はお粥と沢庵二切れ、昼食は麦飯と味噌汁、夕食には野菜のおかずが一品、空腹のあまり食べ物の夢を何度も見ましたが、そんな生活を1週間続けても、自分が元気で生きていることが驚きでした。最後には体が軽くなって雑念が消えたような気さえしました。しかし肉体を持った人間の哀しさ、研修が終了するやいなや、まっしぐらに焼肉屋に駆け込んだことが懐かしく思い出されます。
おかげさまで私は健康に恵まれ、後期高齢者になるまで病気で入院したことがありません。そのせいもあって、私は肉体は動いて当たり前、気合いで動かすものだと思って生きてきました。そして、食べることと自分の肉体との関係を真剣に考えることもありませんでした。
しかし年老いて、酷使してきた身体が疲弊して悲鳴をあげ始めた時、私はやっと自分の肉体に対する感謝と愛おしさを感じることができるようになりました。そして、食のリテラシーの大切さについても考えるようになりました。
肉体はこの世を生きるためのモビルスーツ、それを動かすためのエネルギーを供給するために私たちは食べねばなりません。食べることはこの世の生命をいただくこと、私たちが食べるものは、やがて私たちの肉体になります。そして人間の肉体も地球という生命共同体の連鎖の中にあります。
本草学は、生態学的でホリスティックな学問である。行き過ぎた近代の “divide and rule” の潮流を是正し、生命の全一的機能を回復させる可能性を秘めていると思う。
門外漢ですが、この流水さんのコメントには全面的に同感できます。
流水さんが、アグリセラピーの研究に踏み出されたこと、縁友として心から嬉しく思います。何もお手伝いできないかもしれませんが、陰ながら応援させていただきます。
Akira さま
「未病のうちに治す」という考えは、本草学の基本的な考え方です。その古典が、荘子にあったこと初めて知りました。
Ishikawa さま
「食欲」にはタブーがないという視点、初めて気づかせてもらいました。食には自己管理がどうしても必要なのでしょう。
中川さん
長野県の美ヶ原や霧ヶ峰の美しい写真、高校生の時に修学旅行で訪れ、10年ほど前には還暦修学旅行アゲインででかけましたので、懐かしく拝見しました。
「本草学の魅力」、高橋さんのお話もあって、これも懐かしいなぁと思いながら拝読しました。
私はもともと大学では家畜解剖学を学んで、学位論文もその分野の仕事で書きました。今もって解剖学会と獣医解剖学会の会員ですが、薬学分野での解剖学のちゃんとした教育がされなくなってしまったことを医学領域の先生方からは嘆きをもってうかがいました。
わが国だけ、大学がどんどん自動車学校化していくのが、老人としてはちょっと嘆かわしいかなぁと思います。
「一年の計は穀を樹うるにしかず、十年の計は木を樹うるにしかず、百年の計は人を樹うるにしかず(一年の計画なら農作物を育てるのがよい、十年の計画なら樹木を植えるのがよい、百年の計画なら人間を育てることが重要である・中国の古典「管子」より)」といわれていますが、我が邦では1990年代初頭のバブル崩壊から約30年間にわたって経済が停滞して「一年の計」や「十年の計」に四苦八苦しています。しかしながら、持続的な発展を考えると、ここで踏ん張って「百年の計」を見直し、次の時代を託す人材を育成するためにわがくにの智慧を取りまとめて実践することが欠かせないと思いますが、なかなかね・・
今回も楽しく読ませていただきました。ありがとうございました。
眞鍋昇(東大名誉教授)
眞鍋昇さま
貴重なコメント有難うございました。薬学部で解剖学の授業がないことを聞いて、私も耳を疑いました。人間の骨や筋肉、血管、神経、臓器等の仕組みを体系的に知らずに、どうやって新薬を創るのだろうと思いました。明治維新までは、日本人は大和本草で病気に対処してきました。それが明治以降、医学は西洋医学一辺倒になり、本草学は医学、薬学、鍼灸、整体に分かれました。さらに薬学分野では教育・研究の細分化が進んでいるようです。
私も「ここで踏ん張って百年の計を見直し、次の時代を託す人材を育成する」教育を確立して欲しいです。日本にはそのポテンシャルが十分にあり、そのような人材を育成することが、真の世界貢献だと思います。
流水
中川さん、真鍋さん
お二人の意見に同感です。
薬学部で学んだ者として、現在薬学部で解剖学の授業がないことを聞いてただただ驚くばかりです。
先ずは人間の構造(解剖学)を学ぶことが医療系学部の基本であると思っております。
中川さんが指摘されているように薬学分野では教育・研究の細分化が進んでいるとのことですが、基本の解剖学を学ばずして専門化・細分化された知識を得たとしても、色々な問題に直面した時の問題解決能力のが向上するとは思えません。
もう一度大学での教育の在り方やカリキュラム等を見直す時期に来ているのではないかと思います。
秦正弘
秦正弘 さま
創薬分野のご専門の立場からの貴重なコメントありがとうございました。秦さんが言われるように、実際の新薬開発の現場では、色々な予期せぬ問題に直面して、広い視点からの問題解決能力が問われるのでしょう。有機化学合成の技能だけでは、対処できないのでしょう。
大学の先生方や研究者を目指す学生たちは、”NATURE”や”SCIENCE”などの評価の高い国際誌への論文掲載への思いが強く、それを短期間で効率よく実現させる教育カリキュラム改編が進められた結果だと思います。国際競争に負けないことは大切ですが、日本には日本独自の百年の計の教育システムがあるのではないかと思います。日本にはそのポテンシャルが十分にあると期待しています。
流水
コメント投稿には会員登録が必要です。