縁友往来Message from Soulmates
- 縁友往来
- 失われた35年間
失われた35年間

35歳の時から一年半、アメリカに住んでいたことがある。科学技術庁長期在外研究員として、ミズーリ州立大学食料農業政策研究所(FAPRI)で在外研究を行った。留学先にFAPRIを選んだのは、その前年にFAPRIの研究部長のシュラ―(Gregg Suhler)さんが来日し、そのお世話をしたことからFAPRIに来ないかと誘われたことと、当時FAPRIは世界で初めて世界農業とアメリカ農業の計量経済モデルを開発し、それを使って食料需給予測や農業政策のシミュレーション分析をさかんに行っていたためである。
FAPRIではアメリカのトウモロコシ産業の計量経済モデルを構築し、これを使って気候変動に伴う作柄変動の影響を、緩衝在庫の運営の仕方によってどれだけ緩和できるかの研究を行っていた。最近「令和の米騒動」で備蓄米放出への関心が高まっているが、備蓄在庫の運営の影響をモデル分析していた。この研究は帰国後さらに発展させて、東大に提出した学位論文の中核をなすことになった。FAPRIでの在外研究は、私にとって想い出深い経験である。
ちなみにFAPRIでお世話になったシュラ―さんとその奥様のダイアン(Diane Suhler)さんとは今でも親交がある。FAPRIで初めてお会いした柳島宏治先生とともに、隔週毎にZOOMで開催されている「日本瞑想セッション」に3人は毎回参加してくれている。
私のアメリカ滞在期間は、1989-1990年間であった。今から振り返って見ると、日本経済のバブル経済絶頂期に当たる。日本の貿易黒字の増加とアメリカの双子の赤字の増加が続く中で円高が進行し、一時1ドル75円まで推移した時期である。当時の円の価値は、今のほぼ2倍だったわけである。
三菱地所がニューヨークのエンパイアステートビルを、ソニーがカリフォルニアのディズニー社を買収する噂が流れ、テレビではデトロイトの自動車産業の労働者が日本車をハンマーで破壊する映像が流れていた。日米の経済摩擦が激化した時期であった。外から日本を眺めていて、当時の日本の対外膨張力は凄まじく、このままではまた戦争になるのではないかと本気で危惧したほどだった。
円高が進行していたにもかかわらず、アメリカでは日本車が大人気だった。私の指導教授のアブナー(Abner Womack)先生は、半年待たされて購入したホンダのアコードを大いに気に入っておられた。アメリカの地方都市には地元新聞があり、中古車売買の情報交流コーナーがあるのだが、特に走行距離10万kmを超えた中古車市場では、アメリカ車に比べて日本車の値段が二倍近く高かった。私はせっかくアメリカに滞在しているのだからという理由で、GMの中古車に乗っていたが、とにかく故障が多かった。当時、日本車の故障率は、アメリカ車の10分の1と言われていた。
車だけでなく日本製の家電製品も人気だった。テレビ、CDカセット、PCノートなど、日本製品の価格は韓国製品の3割ぐらい、中国製品の5割ぐらい高かったのだが、お金に余裕のある人たちはこぞって日本製品を購入していた。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の言葉もよく耳にした時期であった。
しかしその後、日本では1990年にバブル経済が崩壊する。1989年末には3万9千円を記録した日経平均株価は90年に入って下落を始め1992年には1万4千円まで暴落した。株価が再び3万9千円を超えるのは、実に34年後の2024年であった。
バブル経済は、通貨流動性が高まる中で実体経済を超えて株価や不動産価格が高騰したもので、何時はバブルははじける運命にあった。しかし日本ではそれへの対応が後手後手に回り、経済不況が長引いた。土地神話を背景に不動産や株を担保に積極融資を行っていた金融機関は巨額の不良債権を抱え込むことになり、この不良債権処理に長期間を要した。
1997年の山一証券と北海道拓殖銀行の倒産は、バブル崩壊後の不良債権問題の深刻さを示す象徴的な出来事であった。それまで日本経済では企業経営が悪化するとメインバンクがそれを支援するというメインバンク制が一般的であったのだが、金融機関が機能不全に陥ってしまったことにより、メインバンク制は後退した。バブル崩壊以降、日本の実質GDPは550兆円前後でまったく伸びなくなり、1人当たり実質GDPはOECD諸国のトップクラスから22位まで低下し、韓国にも追い越されてしまった。
失われた35年間で一番問題だったのは、日本人の実質賃金がまったく伸びなくなったことである。2020年を基準とした日本人の実質賃金指数は、1990年の112から2023年の97へ若干低下した。この間、社会保障負担率は10%以上上昇したので、日本人の生活は貧しくなった。
国全体の平均値で見るとこれが実態なのだが、終身雇用制の組織で働く人には貧しくなった実感は少なかった。これは個人的には毎年の定期昇給で2%づつ給料は上がっていたからである。最も深刻だったのは不正規雇用の人たちである。実質賃金が上がらず、社会保障負担率は上るという影響をもろに受けることになり、不正規雇用者の生活は困窮化した。しかも日本の労働者全体に占める不正規労働者の割合は、この35年間に2割から4割に上昇した。格差社会が形成され、社会の分断化が進行したわけである。
特に若年非正規雇用者の増加は、若者の結婚率と出生率の低下に直結する問題である。長期的には日本の人口減少がさらに加速されることになり、国家にとって喫緊に解決すべき課題であったのだが、政府はこれを傍観して有効な対策を取らなかった。
この35年間どうして実質賃金率が上がらなかったのだろうか。国際的に見ても、先進諸国の中で実質賃金率が上がらなかったのは日本だけである。よく言われたこととして、日本の労働生産性が上がらなかったからという意見がある。しかし、実際には日本の労働生産性はこの間に約3割上昇している。
1998年以降アメリカの労働生産性は50%上昇し、ドイツは25%、フランスは20%上昇した。日本の30%は決して低くなかった。しかし実質賃金率はアメリカが30%、ドイツが15%、フランスが20%上昇したのに対して、日本はゼロであった。
日本では労働生産性の上昇により経営収益が増加したにもかかわらず、その雇用者への分配が行われなかった。経営収益の増加のほとんどは、企業内留保として溜め込まれた。企業内留保額は、この間200兆円から550兆円に増大した。一年間のGDPにほぼ相当する額が企業内留保されることになった。
実質賃金率が上がらないことは、国内の消費者需要が増えないことを意味している。国内需要が増えないため、企業は国内投資を抑制し、海外投資を増やした。国内投資の抑制は国内生産の拡大を抑制し、賃金率の停滞を継続させるという悪循環が形成されてしまったのである。
「失われた35年間」の労働生産性は上昇したが賃金率は上がらないという日本特有の現象の背景には、バブル経済崩壊後、企業が守りの経営に転換したことがある。景気変動を乗り切るには内部留保を積み増しておくことが一番安全と判断したのである。しかしこれでは国内消費は拡大せず、経済は好転しない。さらに政策変数である政府投資も抑制されたままで推移してきたこともある。強い政治的リーダーシップの下で実質賃金率の上昇を目指した制度改革が実施されることが望まれる。
唐突だが、最近の中国や韓国の経済動向を見ていると、日本はやはり安定雇用と技術立国で進んでいくべきだと強く思うようになってきた。グローバル経済の変動に一喜一憂するのではなく、収奪的社会から脱却して、まずは人を大切にし、あらゆる分野で「極める」ことを追求する日本文化の再興が重要であると思う。日本にはそのポテンシャルがまだ十分に残っていると期待している。
2025/9/25

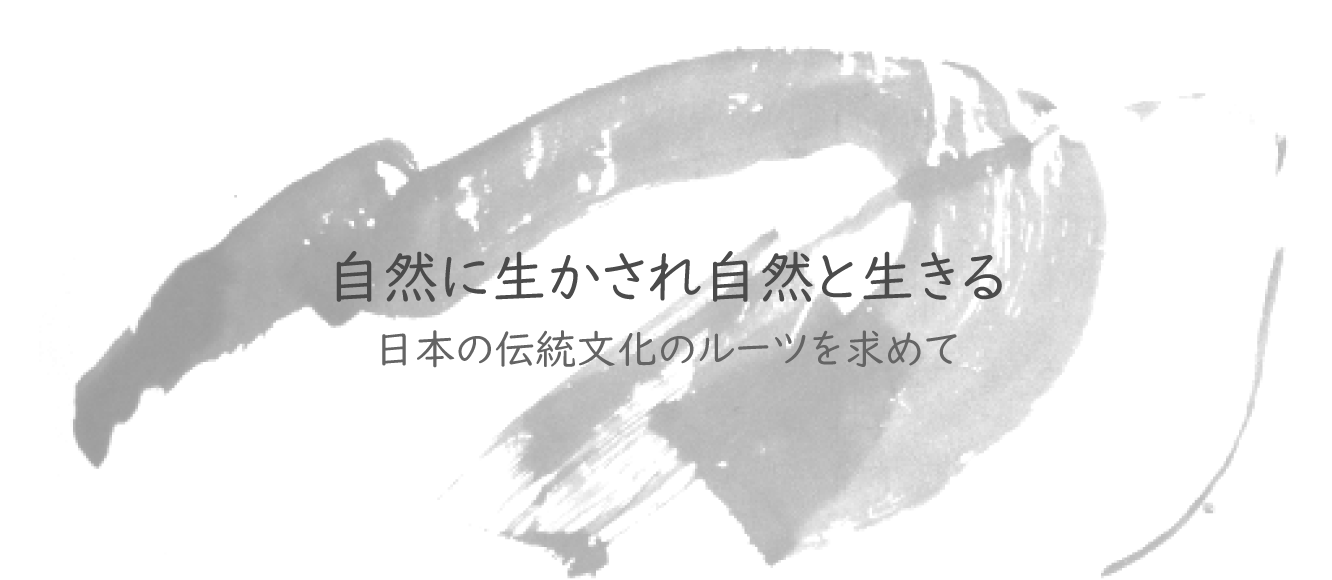
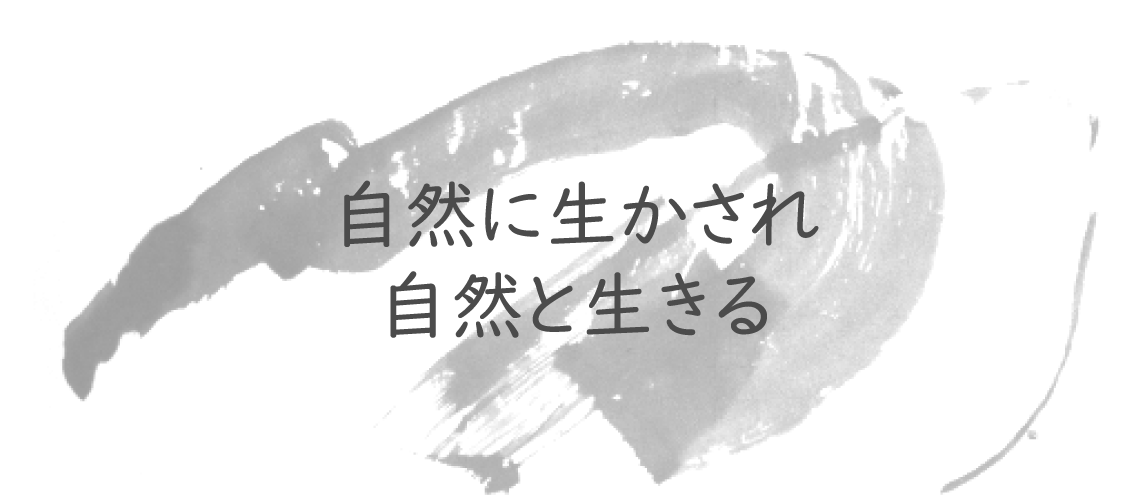
Comment
アメリカ滞在された時の実体験とそれに裏付けられた「失われた35年」につての考察、大変感慨深く読ませていただきました。
「この世の経済の動きを統計データで解析する流水さん」「禅やチベット密教の世界で魂の世界を探究する流水さん」このギャップの大きさが流水さんの不思議な魅力をつくり出しているのではないか、私はそんなふうに感じています。
この両極の世界を「極めよう」とされている流水さんだからこそ、最後の言葉が出てくるのだと思います。
グローバル経済の変動に一喜一憂するのではなく、収奪的社会から脱却して、まずは人を大切にし、あらゆる分野で「極める」ことを追求する日本文化の再興が重要であると思う。
この提言には私も諸手を挙げて賛同します。そのために今何ができるのか、奇跡のように出会えたソウルメイトと一緒にセッションしてゆける幸せに感謝します。
Ishikawa さま
この前の参議院選挙ぐらいから、政治の分野でも失われた30年の問題が正面から採り上げられるようになってきたと思います。バブル経済絶頂期を体験した世代として、失われた35年間を振り返ってみました。最近日本経済再生の萌芽がいたる分野で見受けられるようになってきました。何が真理に近いのか、今年に入ってより鮮明になってきていると感じています。
ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた時代が、懐かしく思い出されました。
想えば、その日本のピークは、戦前、戦中を生き抜き、敗戦後から、日本の奇蹟の経済復興を成し遂げた、
大正世代、われわれの親世代が実現した驚異の復興、発展であったことが分かります。
80年から90年代にかけて、戦前・戦中世代がリタイヤしてから、何か、底が抜けたように、経済だけでなく、あらゆる分野で、日本が劣化してゆく実態が顕著になりました。
その一つが、今回ご指摘して頂いたように、労働生産性が上がっているにも関わらず、国民の実質賃金は低下し、企業内部留保が、なんと倍以上にも膨れ上がりながらも、庶民は、低賃金・低収入に四苦八苦している実態です。そうした事実があるにもかかわらず、経営者も政治家も官僚も、自分のこと目先のこと金のことしか頭にない。当然、悪循環に見舞われているにも関わらず、なんら有効な解決策を講じようとさえしない。
戦前、戦中の日本人なら、すくなくとも疲弊する日本の仲間たちを思いやり、それなりの策を練り実行できる立場にある人間であれば、なんとかしていたはずである。少なくとも、自分の目先の利益に走ることが、最終的に自分の首を絞めることになる末路が、想像できないところに愚かさの悲しみがある。
私の父は、戦後、シベリアのラーゲリで、3年9か月の抑留生活を体験した。私の禅の老師は、地獄のニューギニア戦線の生き残りの捕虜を体験された。二人が、共通して教えてくれた真理がある━。
「自分だけよければいいと思って生きた兵士は、生き残らなかった。なぜなら、絶対に、一人では生きられない状況に直面するからだ。そのとき、戦友の助けがなければ、生きることはできないのだ」
この夏、『ラーゲリから愛をこめて』というテレビ番組を見て、改めて思ったことがある。いかなる状況にあっても、人間として、真心(まごころ)を生きることの大切さだ。
━まずは人を大切にし、あらゆる分野で「極める」ことを追求する日本文化の再興が重要であると思う。日本にはそのポテンシャルがまだ十分に残っていると期待している。━
そのポテンシャルを開花する第一歩が、私たち一人一人のこころの復活から始まるのだと思う。
コメント投稿には会員登録が必要です。