縁友往来Message from Soulmates
- 縁友往来
- 有機体論的世界観
有機体論的世界観

文科省の報告によると、2024年度の小学・中学校の不登校生徒数は35万4千人で、12年連続で増加を続けている。不登校生徒数の増加は、2015年ごろからその傾向が強まり、2015年度の12万3千人から9年間で3倍近くに増加した。
3年ごとに実施される「患者調査」によると、2023年の65歳未満の精神疾患による外来患者数は373万9千人であった。2014年の外来患者数は228万9千人だったので、9年間で1.6倍近くに増加している。
これらの統計値は、我が国の学童や青壮年の精神的ストレスが高まっていることを示唆している。ストレス(緊張)は、現実の自分と理想とする自分像とのギャップが大きければ大きいほど高まる。どうも我が国では理想とする自分像が高く設定され、現実の自分に安らげない社会文化的環境があるようである。この背景には、種々の要因が関係しているであろうが、世界観の適用誤謬の問題も大きいのではないかと考えている。
代表的な世界観には、「機械論的世界観」と「有機体論的世界観」の二つがある。そして現在圧倒的に影響を持っているのは機械論的世界観である。教育や医療、福祉、農業など生命が深くかかわる分野への機械論的世界観の一元的な適用が、種々の問題を引き起こしているのではないかと思う。
機械論的世界観は、機械をモデルとして自然や社会や人間をイメージするもので、全体は部分より構成されているとする要素還元主義的世界観である。有機体論的世界観は、生物有機体をモデルとしてイメージするもので、全体と部分は不可分相即の関係にあり、常に連関性を持って全一的に機能しているとする関係主義的世界観である。
我々が腕時計を分解掃除する時、まず腕時計を個々の部品に分解する。そして個々の部品を洗浄した後、部品を組み立て直すと、腕時計は再び動き始める。腕時計は「機械」であるので、部品に分解しても、部品を組み立て直しても問題は生じない。
これに対して、「有機体」である我々の身体は、個々の部分に分割すると、部分は全体から切り離された段階で機能を停止してしまう。部分を切り取られた身体自身も場合によっては死に至る。一度死んだ個々の部分を組み合わせても、身体が蘇ることはない。
この様に、腕時計の場合と身体の場合では、全体と部分の関係が大きく異なっている。しかし効率性を追求するあまり、人間が有機体であることを忘れて、教育や医療、福祉の制度設計が行われているのではないかと危惧している。有機体である人間の成長モデルを基準にして、社会システムの設計を行わなければ、現実の自分に納得して安らぐことはできないであろう。
機械に比べて有機体の特徴は、環境を含む他者との繋がりの中で成長し、種を継ぐことである。機械は孤立しても存続できるが、有機体は他との繋がりが切れると生きていけない。有機体は、個体レベルでも種レベルでも常に動態の中で存続している。
先日の「日本瞑想セッション」でアッチャラヤ(阿闍梨)のジョティ(Jyoti)先生は、ヒンズー文化圏では人間を5つの層の総体として理解していることを紹介された。ヒンズー文化圏では、ヨガの実践体験から、①肉体、②エネルギー体(エーテル体)、③感情体(アストラル体)、④叡智体(メンタル体)、⑤歓喜体(スピリチュアル体)の5層からなる人間モデルを伝統としているそうである。
アッチャラヤのアヌパム(Anupam)先生は、さらにこれら5層の働きを認知する「内なる光」の存在を説明された。Osho(和尚)は、これら5つの層の上位にさらに⑥宇宙体、⑦涅槃体があることを説明している。要するに人間は多次元的に成長する潜在力を秘めた有機体であることを解説している。
空海は「十住心論」で人間の心が①異生羝羊心(凡夫の羝羊のような心)から⑩秘密荘厳心(自己の心に曼荼羅の荘厳があることが自覚される心)まで10段階成長することを解説しているが、これも多次元的な人間成長モデルといえる。大乗仏教の唯識論も、心の根本煩悩、隋煩悩、極微細煩悩の退治を通じて、菩薩位や仏位に到達することを目指す人間成長モデルといえよう。
平板な機械論的な人間モデルではなく、成長や超越が組み込まれた有機体論的な人間モデルを基準とした社会システムの構築により、我々が生涯を通じて十全な成長を遂げ、生命の深みを実感して生きられる社会の実現が望まれる。
2025/11/25

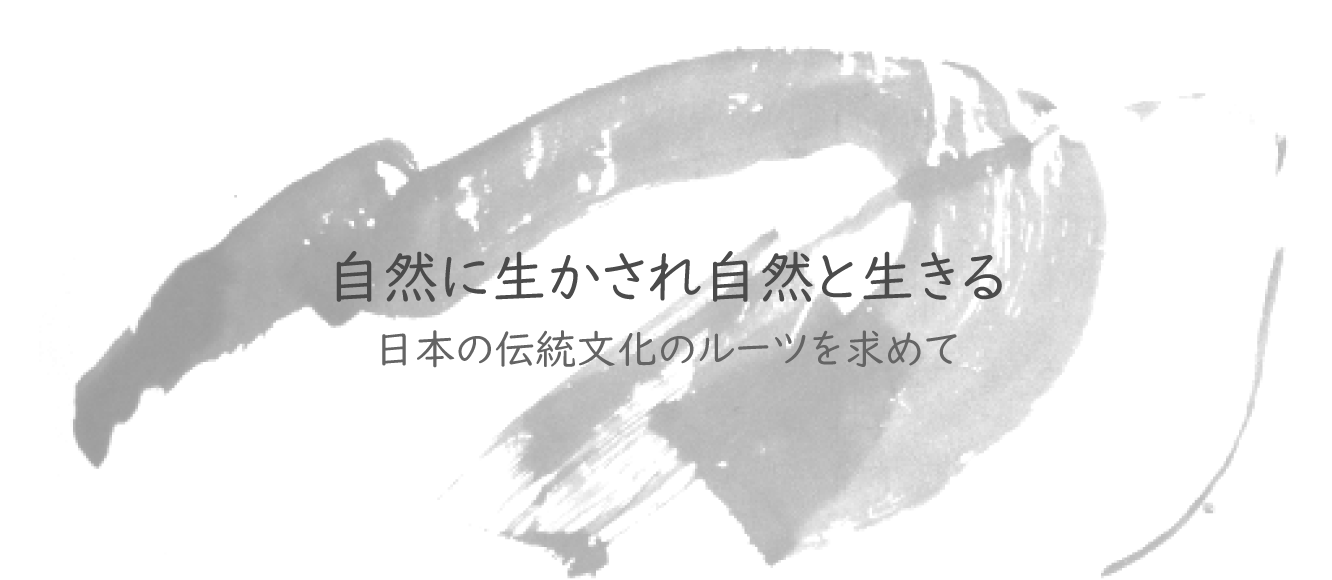
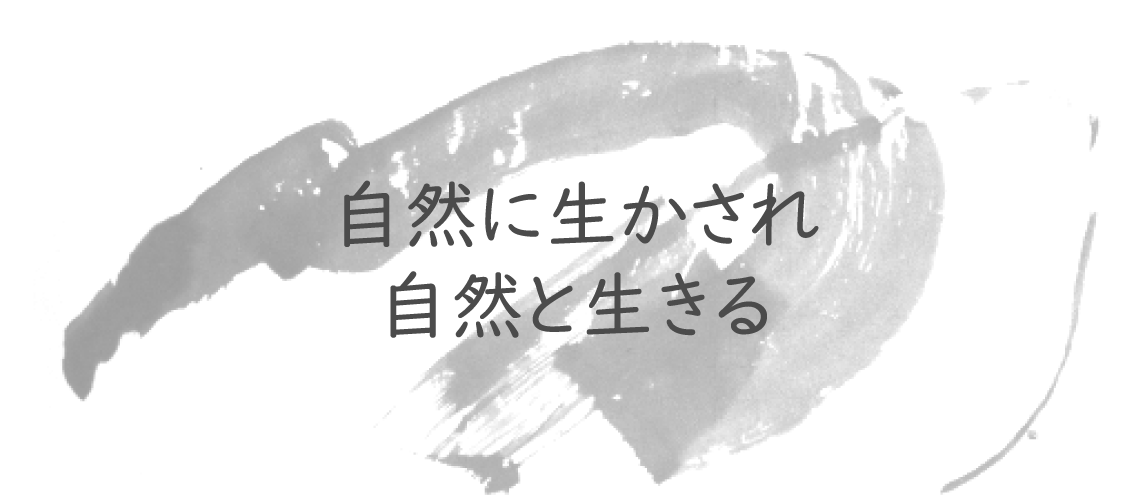
Comment
素敵な写真ですね。優しい光に包まれた大樹の写真を見て、思わずこの大樹のもとに身を寄せたくなりました。
この世では今、社会不安を背景に「寄らば大樹」という風潮が一段と強まっているようです。学校教育が、この大樹のように子供たちを優しく惹き寄せてくれれば良いのですが、現実はどうやら正反対の方向に動いているようです。
インターネットやAIなどの先進テクノロジーによって、子供たちを取り巻く情報環境は激変しています。時代のスピードに追いついて行けなくなってしまった日本の学校教育システムが、不登校生徒数を増加させているように私には思えてなりません。
流水さんがコメントされているように、自他を別々のものとする「機械的世界観」を子供たちに強要する教育が、この問題の根底にあるのだとしたら、いくらインターネットやAIの使用を規制しても、この潮流に歯止めをかけることは難しいのではないでしょうか。
若者の半数以上が、魂の存在と転生輪廻を信じているという調査報告があります。もし今の私が10代の少年に戻れるとしたら、時代とズレてしまった「機械的世界観」に基づいた教育システムを強要されることを拒絶すると思います。
流水さんのおっしゃる通り、時代は「成長や超越が組み込まれた有機体論的な人間モデルを基準とした社会システム」の構築を求めています。しかし、「機械的世界観」と権威主義によって形骸化してしまった現在の教育システムを変革するのは、容易なことではありません。
最近ではコンプライアンスの遵守がますます厳しくなって、学校という組織の中で改革を実現するのはますます難しくなっています。対処療法かもしれませんが、フリースクールや「好きなこと」で繋がった仲間との活動など、ドロップアウトした子供たちを受け止める「場」を充実させることが急務だと思います。
子供達は大人を見て育ちます。自分の心が物質の次元から自由になっていなければ、子供たちを自由にすることなどできません。
私たちひとりひとりに今できること、それは、たとえこの世の価値観からはみ出したとしても、生き生きと生きてゆける道があることを、己の生き様で示せる大人になることではないでしょうか。
ご指摘の通り、私も青年期、「平板な機械論的な人間モデル」に、魂が窒息しそうな苦しみを味わった一人として、こころから本論の趣旨に共感するものです。
◎「「有機体」である我々の身体は、個々の部分に分割すると、部分は全体から切り離された段階で機能を停止してしまう。部分を切り取られた身体自身も場合によっては死に至る。一度死んだ個々の部分を組み合わせても、身体が蘇ることはない。……効率性を追求するあまり、人間が有機体であることを忘れて、教育や医療、福祉の制度設計が行われているのではないかと危惧している。有機体である人間の成長モデルを基準にして、社会システムの設計を行わなければ、現実の自分に納得して安らぐことはできないであろう。」
まったく、その通りだと思います。人間が、生命として、生物レベルにおいて、「安らぎ」を得られないシステムの中に閉じ込められること━。そこにいるのが嫌で、いることができなくて、必然的に学校を拒否するのは、自然の理であると言えるかもしれません。子供たちが、自ら命を絶つとところまで追いつめられる状況は、何としても変えてゆかねばなりませんね。
◎「機械に比べて有機体の特徴は、環境を含む他者との繋がりの中で成長し、種を継ぐことである。機械は孤立しても存続できるが、有機体は他との繋がりが切れると生きていけない。有機体は、個体レベルでも種レベルでも常に動態の中で存続している。」
この「機械は孤立しても存続できるが、有機体は他との繋がりが切れると生きていけない。有機体は、個体レベルでも種レベルでも常に動態の中で存続している」とは、極めて重要な指摘であると思います。
個体レベルでも、種レベルでも交流・呼吸し、さらに自然・宇宙とも交流し呼吸している「実態」から離れて論じられる、いかなる社会システムも、最終的には永続性を持たず、砂上の楼閣とならざるをえない必然の根拠であると思われます。自然の理(フランシス・ベーコンも言うように、人間も自然の法則に則り、その中でのみ生かされている)に、反しているのですから。
◎「平板な機械論的な人間モデルではなく、成長や超越が組み込まれた有機体論的な人間モデルを基準とした社会システムの構築により、我々が生涯を通じて十全な成長を遂げ、生命の深みを実感して生きられる社会の実現が望まれる。」
心の底から、賛同します。「我々が生涯を通じて十全な成長を遂げ、生命の深みを実感して生きられる社会の実現」━。私も、そうした社会の実現に向けて、非力を承知で(笑)、尽くしてゆきたいと思います。貴重な方向性を示していただき、有り難うございました。
コメント投稿には会員登録が必要です。