愚老庵ノートSo Ishikawa
劣化した日本を振り返る

「日本が劣化している」最近、同世代の親しい友人たちとの会話の中で、このことがよく話題に上ります。「日本が衰退している」と感じる日本人は、2016年には 40%だったのが、2024年には 70%になったと、イプソスの世論調査は報告しています。
国連の統計では、GDPこそ世界第4位ですが、日本人一人当たりのGDPは、韓国に抜かれ43位まで下落しました。平均賃金がアメリカの40%、貧困率が15,4%、日本人の7人に1人が年収127万円以下で生活しているという数字は、「日本が衰退している」ことを物語っているようです。
衰退しているのは経済だけではありません。学術の分野でも、世界大学総合ランキングで東大は35位、京大は61位という調査結果が出ています。少子高齢化が進行し、国の債務残高が膨らみ続けている現状を見ていると、日本の劣化はこれから先さらに進行してゆくように感じます。
何故こうなってしまったのでしょう。「それは私たちが豊かになってハングリー精神を失くしてしまったからではないか」友人の一人が発した言葉に皆が頷きました。
私たち団塊の世代は、戦後の「物のない時代」に育ちました。給食でユニセフが支援してくれた脱脂粉乳を飲んで足りない栄養を補いながら、アメリカの物質的な豊かさと先進的なライフスタイルに憧れる、そんなハングリーな少年時代を私たちは過ごしてきました。
テレビや冷蔵庫、ステレオやクーラーなど、新しい電化製品が初めて家に届いた時の皆んなの嬉しそうな顔。今振り返ると、物質的な充足感が心を幸せにしてくれる時代、そして未来に希望があった時代、そんな時代に私たちは育ったのかもしれません。
私たちの青春時代は高度経済成長期でした。給料は右肩上がり、私たちは「ハングリー精神」をエネルギーにして懸命に働き「憧れていたモノ」を次々と手に入れることができました。
やがて、家電や自動車だけではなく、ウオークマンやゲーム機、カメラやビデオなど、日本ならではの「ものづくり」から生まれた製品群が世界を席巻しました。Made in Japanが大衆消費社会を牽引して、Japan as No1 と言われる時代がやってきたのです。
Akira さんは「縁友往来」への寄稿「遺伝子とIQが物語る日本人と日本文化のルーツ」で日本人のDNAと潜在意識のポテンシャルの高さに言及していますが、この潜在力があったからこそ、私たち日本人は世界をリードする画期的な製品群を誕生させることができたのではないかと思います。
しかし、日本が「ものづくり」によって輝いていた時代は、長くは続きませんでした。強くなりすぎた円を是正するための金利引き下げによって、バブルの時代が始まったのです。
多くの企業がダブついた資金を不動産や株式に投資し、先を争って「財テク」に走りました。本業の「ものづくり」で地道に生きてきた人たちから見ると、これは実体経済とはかけ離れた「賭博」の世界でした。
お金がお金を産むことはあっても「賭場」からは生活に必要な物資は何ひとつ生まれてきません。「自分だけが儲かればいい」「お金がすべて」というマネーゲームの狂乱は、日本という国の精神を確実に劣化させたと私は思っています。
バブル経済とその崩壊は、日本の国土と国民に大きな傷を残しただけではありません。その後遺症で、それから30年もの間、日本はデフレ・スパイラルから抜け出すことができませんでした。
一度贅沢な暮らしをしてしまった人は、生活レベルを落とすのが難しいと言われます。バブルが弾けた後、大多数の日本人は、これまで築き上げてきた生活を失う恐怖心から一斉に「守り」に入りました。
私たちが選んだのは、痛みを伴う変革によって新しい未来を拓く道ではなく、現状に甘んじて根本的な課題を先送りする道でした。そして、30年という月日が流れ、気が付くと私たちを牽引してきた「ハングリー精神」と「未来への希望」は、いつの間にか失われていました。
「守り」に入った人や組織は、失敗を恐れて前例を踏襲し、リスクを冒さず縄張りと既得権益を守ろうとします。成果を出すことよりも失敗しないことが評価される土壌からは、世界をリードするような画期的なイノベーションは生まれてきません。
ハラスメントと言われるのを恐れて「切磋琢磨」することが出来なくなってしまった組織からは、来るべき「破壊と再生の時代」を担う人材は育ちません。
バブル崩壊後の「失われた30年」、この停滞した長いトンネルをつくり出したのは、「物質の豊かさ」の中で「便利で快適な暮らし」というぬるま湯に浸かってハングリー精神を喪失し、いつしか眠りに落ちてしまった「私たちの魂」だったのではないか、私はそう思っています。

戦後の日本で、もうひとつ失われたものがあります。それは「人と人との絆」です。欧米流のライフスタイルが普及するにつれ、「個人主義」が私たちの意識に浸透し、行動を支配するようになりました。
子供だった頃、私たちは個人の利害よりも集団の利害を優先する「集団主義」の中で育ちました。そこでは、集団の中で協力し合い、礼儀やマナーを守り、相手を気遣うことが重視されていました。
今でこそ日本の集団主義の良さが世界から尊敬されるようになりましたが、その当時、欧米流の「個人主義」に憧れを抱いていた私たちは、時代遅れの価値観とルールを押しつけられているように感じていました。
血縁と地縁に縛られた家制度とムラ社会、組織に染み込んだ年功序列と滅私奉公の風習。周囲の眼を気にしながらこれまでの常識や暗黙のルールを守る生き方に、私たちは疑問を持つようになりました。
1960年代後半、大学に入学すると、キャンパスには世界中で同時発生した反体制運動とカウンターカルチャーの嵐が吹き荒れていました。学生運動には違和感を感じ、ヒッピーのコミューンに心惹かれながら、私はこれまで確かだと思っていた世間の価値観や権威を、次々と自分の中で「自己否定」してゆきました。
この時代、権威を否定し個人の権利や自由を尊重する「個人主義」は、世の中の様々な既成概念の呪縛から、私たちの意識を解放してくれたと思います。しかし、それと引き換えに、「人と人との絆」が、日本の家庭や地域社会、学校や会社などから失われてゆくことなど、当時の私には考えも及びませんでした。
1990年代に入り、ソビエト連邦が崩壊しアメリカが単独で世界の覇権を握ると、あらゆる国の体制をアメリカ型につくり変え、グローバル企業の世界進出を後押ししようとする動きが拡がってゆきました。
この時代、アメリカの掲げる高邁な理想の裏側で、世界を支配し利権を搾取しようとする一部の支配者層の存在も明らかになり「個人主義」の負の側面も露わになりました。
飽くなき利益を追求し弱肉強食の世界を生きる支配者層にとって、人は搾取する対象か戦う相手でしかありません。奪い取ったものはいつ奪い返されるかわかりません。獲得したものが大きくなればなるほど不安と恐怖心も大きくなります。
強欲な支配者層の掲げる「個人主義」はその恐怖心のゆえに、自らを守る「鉄壁な防衛」を必要としました。そしてそれは、強大な軍事力だけにとどまりません。
アメリカでビジネスをしようとすると、あらゆるリスクを想定して細部まで定めた契約書の分量に驚きますが、これも、恐怖心が造り出す過剰な「防衛」の産物なのではないでしょうか。
やがてアメリカ流の「個人主義」と人間不信を前提としたビジネススタイルは、グローバルスタンダードとなり世界中の国々に広がってゆきました。
そしてインターネットの普及とITテクノロジーの進化によって、私たちは個人情報を守るために、他人との間にさらにもっと強固な防壁を築かなければならない時代を迎えることになります。
特殊詐欺や悪質なセールス、犯罪から身を守るために、固定電話を留守電にしておかなければならない時代がやって来るとは、子供の頃には夢にも思いませんでした。
日本では、この半世紀の間に「人と人との絆」が、どんどん希薄になりました。近所付き合いは無くなり、冠婚葬祭に集うのは家族だけになり、かつて生活共同体だった「日本株式会社」の多くは、利益を優先するビジネスの場に変貌しました。
コロナ禍は追い討ちをかけるように、家族や親しい友人との絆をも分断しました。そして、リモートワークは仕事の場でも、人と人とが「生で」触れ合う機会を駆逐してゆきます。
SNSに人との絆を求めても、そこにあるのは「映え」を意識した表面的な付き合いだけで、逃げ場のないリアルな現実を共に生きることから生まれる「深い絆」や、切磋琢磨しながら一緒に何かをつくり上げる歓びと感動は、そこからは得られません。
人は一人では生きてゆけません。私たちは人と出会い、人と繋がることによって生きるエネルギーを引き出されます。そしてそこには、自分一人ではつくり出せない「エネルギー場」が生まれ、それが人間を活性化し成長させるのではないでしょうか。
この半世紀の間、私たちは集団主義の呪縛から自由になるために、様々な「しがらみ」を断ち切ってきました。そして束縛のない「自由で快適な暮らし」を守るための防壁を構築し「人とのつながり」を次々と遮断してきました。
「人と人との絆」が失われることによるエネルギーの低下、これが日本を劣化させた様々な原因の根底にあるのではないか、私はそう考えています。

これから日本はどうなるのだろう、そんなことを考えているうちに、ふと江戸時代の庶民の暮らしのことが心に浮かんできました。
江戸の長屋には薄い壁しかありませんでした。隣の様子は筒抜けで、プライバシーなど無きに等しい生活でした。そこでは、一つしかない狭い部屋がダイニングになり、リビングになり、そしてベッドルームにもなりました。子供部屋などありませんから、引きこもりが存在する余地などあろうはずもありませんでした。
個室で仕切られていない居住空間、そこには、貧しさや不便さゆえに、身を寄せ合い助け合って生きなければならない簡素な暮らしがありました。しかしその環境があったからこそ、緊密な絆で結ばれた温かいコミュニティが生まれたとは言えないでしょうか。
パリの人口が50万人と言われていたこの時代に、江戸では100万人の大都市が形成され、多様な庶民の文化が花開いていました。そしてそこには、自然と共生する暮らしがありました。
封建的な身分制度の下であっても、無駄のない最小限のエネルーギー消費によって、地球に優しい循環型の社会システムがこの時代に実現されていたのは驚きです。
人が感じる豊かさや幸福感は、周りの人との比較によって決まるという研究報告があります。物質的に貧しくて不便な生活でも、周りが皆そうであれば、そこで暮らす人は、自分が不幸だとは感じないというのです。
物質的な豊かさの中にありながら、個人も社会も劣化し貧富の格差が拡大する日本、その未来を考える時に、江戸のコミュニティは、大きなヒントを与えてくれるように思います。
劣化した日本を再生するために私たちに今何ができるのか、私は、自分が歩んできた道を振り返り、「物質的な豊かさ」に囲まれ「安全な砦」の中で眠りに落ちてしまった己の魂を、もう一度リセットするところから始めようと思います。
「縁友往来」では今、人と人との絆が再生されつつあります。このステージのセッションから生まれる新たなエネルギーの共振が、日本を再生してくれることを心より祈っています。
LINKS
今月のNATURE通信は、「早春の光と風」を求めて
富士山周辺、鹿島灘と偕楽園をロケしました。
NATURE通信February 2025 「早春の光と風」
https://nature-japan.com/cat_nature/mar2025/
「縁友往来」に新しい投稿があります。
エコノミカル・コレクトネス by 流水
https://grow-an.com/mate/mate-025/
私の内宇宙の旅『真理大全』━科学で迫る心の不思議 by Akira
https://grow-an.com/mate/mate-024/
『真理大全 真理篇・科学篇・思想篇』のご案内 by Akira
https://grow-an.com/mate/mate-023/
2025/3/24

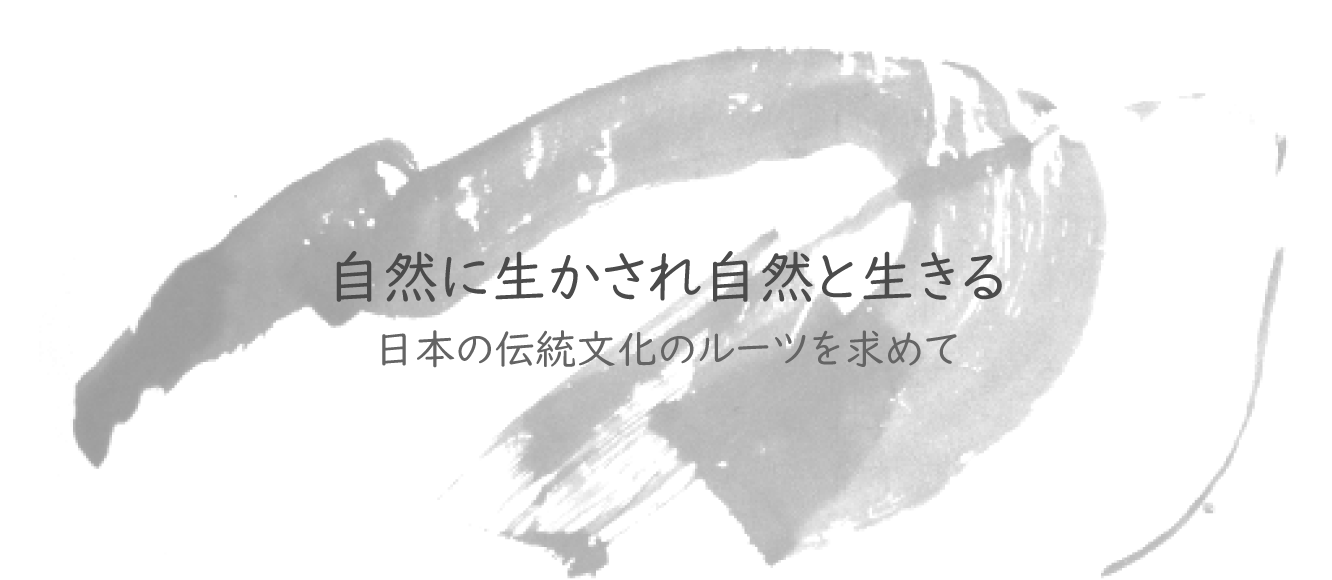
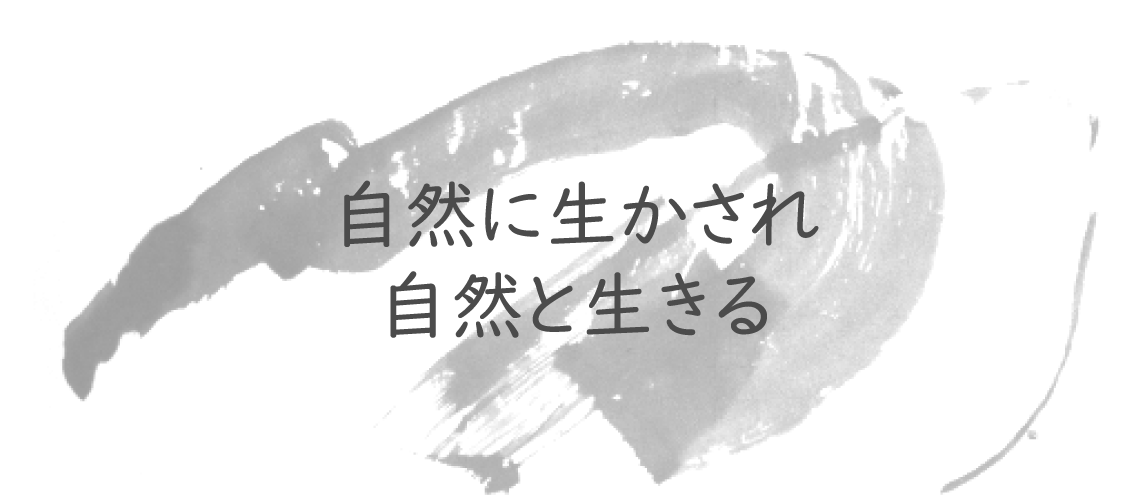
Comment
コメント投稿には会員登録が必要です。