愚老庵ノートSo Ishikawa
「遠野」里山紀行

一ヶ月ほど前、「夏の焚き火」を収録するために、岩手県の遠野を訪れました。このロケは、深夜に出発し翌日に日帰りする、いつもの「ひとり弾丸ロケ」ではありませんでした。
今回は、NATURE JAPANを英訳してくれているBrianが一緒で、遠野を拠点に活動する建築家の清水さんが現地で出迎えてくれました。
車で日帰りできないところまで東京を離れ、40年来の気のおけない友人たちと一緒に過ごす二泊三日の旅は、いつものNATUREのロケとは違う「ゆったりとした時間」をつくり出してくれました。
今回の愚老庵ノートでは、この「遠野の旅」を振り返り、そこで心に浮かんだことをレポートさせていただこうと思います。
馬と人が共に暮らす森と里山の環境を体験してもらうことをコンセプトにワークショップを展開しているクイーンズメドウ・カントリーハウス、この施設は運営スタッフが休暇に入っていることもあり、自然の静けさに包まれていました。
新宿御苑とほぼ同じ広さの里山には、今回の焚き火の仕掛け人で、アドバイザーとして此処の活動をサポートしている清水さんと、同行してくれたBrian、そして私の三人しかいません。
宿泊棟にはテレビがありません。聞こえてくるのは、野鳥の囀りとエゾハルゼミの鳴き声、そして時折、広葉樹の葉を揺らす風の音だけです。ここには、地を這うように渦巻いている耳慣れた「都会のノイズ」がないのです。
この環境の中で夜を過ごしてみて、自分がいかに現代文明がつくり出した「人工のリズム」の中で生きていたのか、あらためて気づかされました。
私たちが泊まった宿泊棟には同じ屋根の下に厩があり、馬の気配を遠くに感じながら眠りに就くことになりました。
この地方では馬を家族のように大切にし、身近な場所で世話するために「南部曲がり屋」という独自の建築様式が生まれました。私たちが泊まった宿泊棟の設計には、人と馬が共存し自然と調和した生活を営むための、この「伝統の知恵」が取り入れられているそうです。
機械化が進む以前の農家にとって馬は大切な労働力でしたが、ここの馬たちは使役されることなく、自由にのびのびと過ごしています。自然と共生する馬たちとの暮らしに「癒し」を求めて、都会から様々な人がこの地にやって来ると清水さんは言います。
翌日、馬たちが歩き回る里山の田圃で、ひとり黙々と田植えをする女性を見かけました。地元の方かとばかり思っていましたが、後で東京から来たクラシックの演奏家だと聞いて驚きました。
私自身も、愛犬のおかげで「愛する力」を蘇らせてもらった経験があるので、アニマルセラピーの力を信じていますが、この遠野の里山が、馬によるセラピーの隠れた聖地になっているとは知りませんでした。
馬たちは、焚き火を収録している私たちに興味津々で、何度も様子を見に来ました。焚き火の画面に意識を集中していている時に、ふと気配を感じて後ろを振り返ると、そこで馬が見守っているのです。
あの世に旅立った愛犬が元気だった頃、私が何をしているのか、時折そっと見回りに来ていたことが思い出されて、思わず胸が熱くなりました。焚き火収録中の馬たちとのこの不思議な触れ合いは、忘れられない遠野の思い出になりました。
 Photo by Keiji Shimizu
Photo by Keiji Shimizu
日本に住んで40年になるBrianは、古民家と里山に惹かれて、日本全国を旅しているのに、何故か遠野を訪れたことがなかったそうです。
「今までこんな場所はなかった。ここには昔の日本の気配がある」Brianはそう言って、初めての遠野体験に、しきりに感動していました。
劇的な四季の気候変化が遠野の美しい自然風景を造り出し、その自然と共生してきた「古き良き時代の日本の原風景」が遠野には今も色濃く残っている、清水さんはそう語ります。
民俗学者の柳田國男が、この地方に伝わる伝承や民話をまとめた「遠野物語」によって、遠野は広く世に知られるようになりました。
そこに書かれた座敷童子や河童や雪女などが、今にも現れて来そうな幻想的でどこか懐かしい遠野の風景、それが訪れる人を魅了するのかもしれません。
しかし、Brianは何故、遠野にだけ「昔の日本の気配」を感じとったのでしょう。その解答を探して、遠野博物館に立ち寄ってみることにしました。
遠野博物館には、遠野の歴史と伝説を物語る様々な資料が展示されています。近代化される前の里山の記録写真や当時実際に使われていた生活道具は、かつての遠野の気候風土と生活環境がいかに厳しいものだったかを伝えてくれました。
展示場を巡るうちに、私は一枚の絵の前で釘付けになりました。それは「間引き絵馬」と題された絵で、そこには母親とおぼしき女性が、生まれたばかりの赤子を口減らしのために「間引く」様子が描かれていました。
「飢饉によって間引かれ川に流された赤子が、神様のもとに流れ着き、河童になった」 河童伝説にそんなルーツがあったことを、恥ずかしながら私は知りませんでした。
この地に、口減らしのため「間引き」や「姥捨て」などの風習が存在し、度重なる凶作で餓死した人々を供養するために五百羅漢像がつくられたという哀しい歴史は、「飢餓と貧困の時代」が、日本にあったことを思い出させてくれました。
厳しい自然環境の中で、死と隣り合わせで生きる人達は、自分たちの力を遥かに超えた「目に見えない存在」に手を合わせ、救いを求めます。
神仏を身近に感じるこのような暮らしがあったからこそ、遠野には、この世と異界を繋ぐ様々な伝承や民話が生まれのかもしれない、そんなことを感じました。
「飢餓と貧困に苦しまないためにどうすればよいのか」 近代に入り、私たち日本人は、その道を模索しました。
そこには二つの道があったように思います。ひとつは、厳しい自然環境を受け入れて一蓮托生で自然と共生する道、そしてもう一つは、科学技術の力で自然を支配し物質的な豊かさを獲得する道でした。
遠野の地に生きた先人たちは、農業や畜産、林業や狩猟などによって、厳しい気候風土と共生する暮らしを選びました。その選択のせいか、遠野の歴史には、近代日本の繁栄を築き上げた「工業化と大量生産」という産業の「匂い」が感じられないのです。
「遠野は汚れていない」というのが、Brianの遠野の第一印象だったそうです。私も遠野に、現代の物質文明に染まりきっていない「清浄な気配」を感じていました。
それは遠野の人達が、近代化によって「富国強兵」と「殖産興業」を目指してひた走る時代のメインストリームから少し離れたところで、里山で馬と一緒に暮らす「心の豊かさ」を大切にして、ひっそりと生きてきたからなのではないでしょうか。
Brianが何故遠野に「昔の日本の静謐な気配」を感じたのか、その疑問の答えが見つかったような気がしました。

遠野は、東日本大震災を救援する拠点として、一時、賑わいを見せましたが、その後は、高齢化と人口の減少が止まらないそうです。これから先、遠野は限界集落として衰退してゆくしかないのでしょうか。
かつて遠野とは別の道を選択した私たちは、自然を己の欲望を満足させるための物資とみなし、物質的な豊かさを享受するために、巨大で複雑な社会システムをつくり上げました。
そして今、この便利で快適な「超管理社会」で生き残るために、熾烈な競争と厳しいコンプライアンスの遵守を求められ、そのストレスで心身を病む人たちが増加しています。
「人間の本当の幸せとは何か」 遠野は「物質に幸せを求める」ことに疲れた人たちに、その答えを探すための「ステージ」を提供することができるのではないでしょうか。そしてそれは、遠野という風土だからこそできることなのだと私は思います。
Brianが感じた遠野にしかない「静謐な気配」を貴重な遺産として、自然と共生する「地域おこし」によって、この地が再生してくれることを願わずにはいられません。
東京への帰り道、東北道を花巻から仙台に向かう途中で、車窓に広がる景色から「静謐な気配」が少しずつ失われてゆくのを感じました。
そして、東京に近づくにつれ「都会のノイズ」が大きくなり、物質への飽くなき欲望が生みだす「人工のリズム」の巨大な渦の中に突入してゆくような感覚がしました。
遠野に移住して8年になる清水さんは、東京に近づくと頭が痛くなってしまうと言っていましたが、それがわかるような気がしました。
NATUREを極めようとするのなら、東京を離れて「静謐な気配」の中で制作を続けるほうがいいのではないか、そう言ってくださる方もいますが、私は今のところ、東京を離れるつもりはありません。
大都会の「人工のリズム」に幾重にも包囲されて、魂が窒息しそうになるから、必死で、大自然が奏でる「生命のリズム」を求めようとするのです。
人間の煩悩が渦巻く「無明の闇」の中で、人間の業の深さに絶望し救いを求めるからこそ、神秘的な自然の美しさに出会えた時、そこに差し込む「神仏の光」を感じることができるのです。
東京を離れ「静謐な気配」があたりまえの日常になってしまったら、NATREに対するこのような強いモティベーションは、きっと失われてしまうでしょう。
「何故私が、東京で暮らしながらNATUREを制作し続けるのか」今回の遠野の旅では、その解答を見つけることもできたような気がします。
LINKS
今月のNATURE通信は、遠野で収録した「焚き火」がメインテーマです。
NATURE通信July 2025 「夏の焚き火」
https://nature-japan.com/cat_nature/jul2025/
「縁友往来」に新しい投稿があります。
The Immensity of a Forest—生命共同体の一員になるには by Brian Amstuts
https://grow-an.com/mate/mate-033/
亡き妻の“声”に救われた心理学者ー秘めた光を放て By Akira
https://grow-an.com/mate/mate-034/
ネパールとのご縁 By 流水
https://grow-an.com/mate/mate-035/
参照
2025/7/25

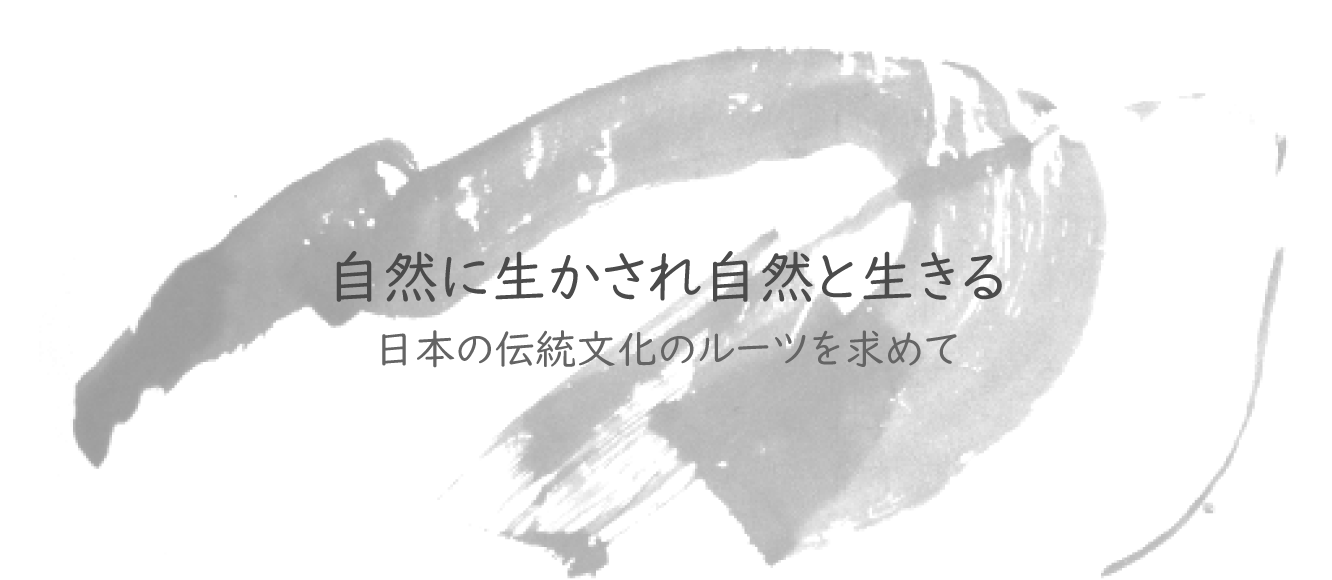
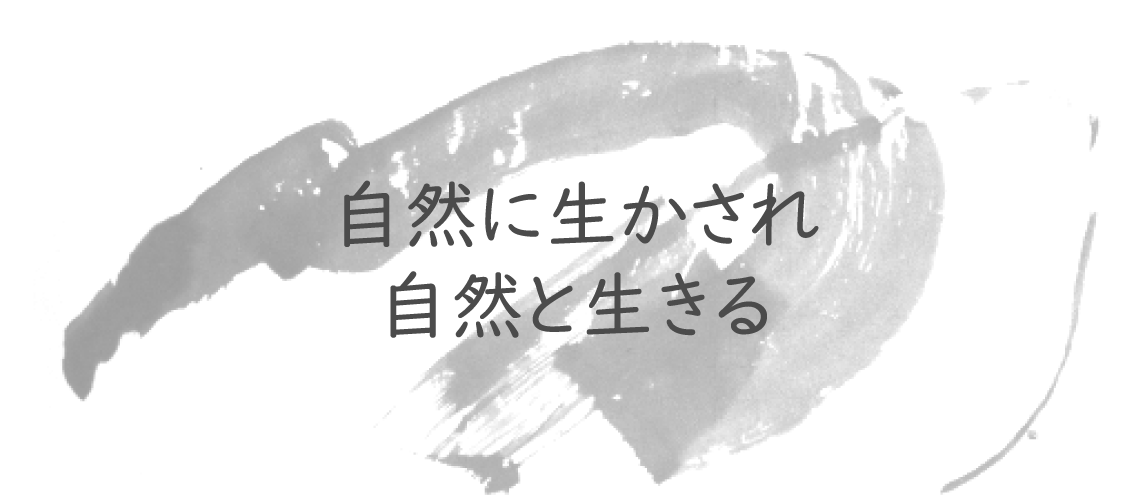
Comment
闇にこそ、光は輝く。闇は、光に勝てない━。
愚老庵さんのエッセイを読み、次の最後の言葉に感動しました。
人間の煩悩が渦巻く「無明の闇」の中で、人間の業の深さに絶望し救いを求めるからこそ、神秘的な自然の美しさに出会えた時、そこに差し込む「神仏の光」を感じることができるのです。
東京を離れ「静謐な気配」があたりまえの日常になってしまったら、NATUREに対するこのような強いモティベーションは、きっと失われてしまうでしょう。
「何故私が、東京で暮らしながらNATUREを制作し続けるのか」今回の遠野の旅では、その解答を見つけることもできたような気がします。
私たちの人生にも通じる真実が、この言葉にはあると思いました。
誰もが体験する、救われ難い絶望、恐怖、挫折、喪失の痛み、…
しかし、こうした深い闇があるからこそ、その闇を数ってくれる光を
求めるのが人間ではないでしょうか。私も、70年近くを生きてきて、
人生は、求めるなら必ず、体験した闇を超える光に出会えるようになっていると確信をもって言うことができるようになりました。
それは自分だけでなく、ご縁のあった多くの方が証明してくれた真実です。
「縁友往来」筆者の一人、流水さんから以前、紹介された和尚の言葉を、愚老庵さんと、ご縁のある皆様に贈らせていただきます。
あなたの根は、地にもぐり
最も深い地獄にまで達する必要がある。
罪人が、賢者になるとき
その賢者には、ある美しさがある。
賢者が一度として罪人になることもなく
ただ賢者であったなら、
彼は、ただの単純な馬鹿だ。
彼は、生をとり逃がしているのだ。
コメント投稿には会員登録が必要です。